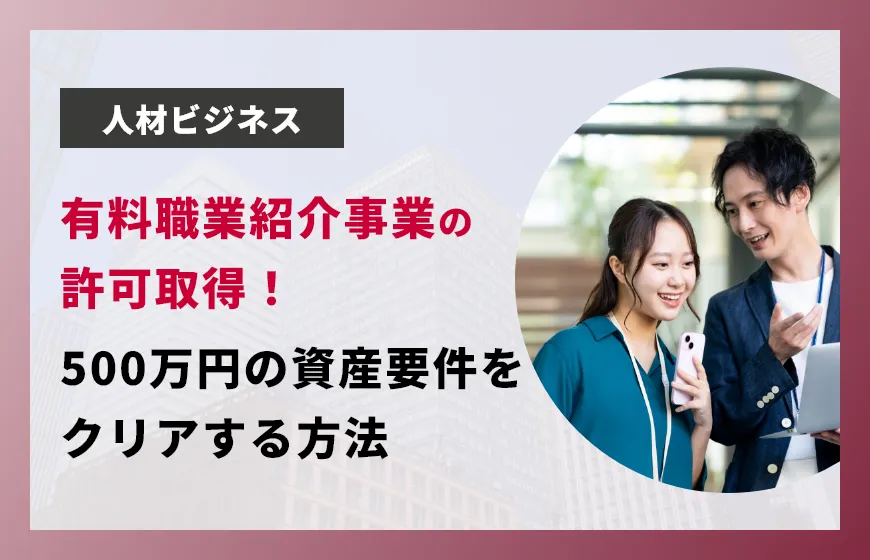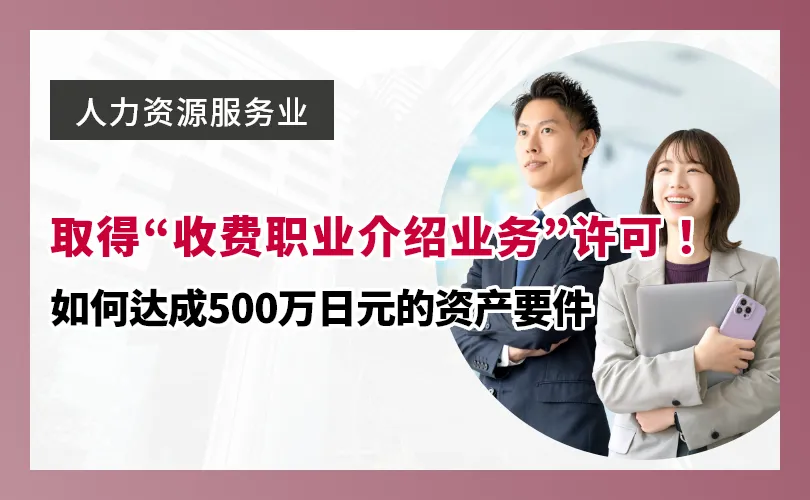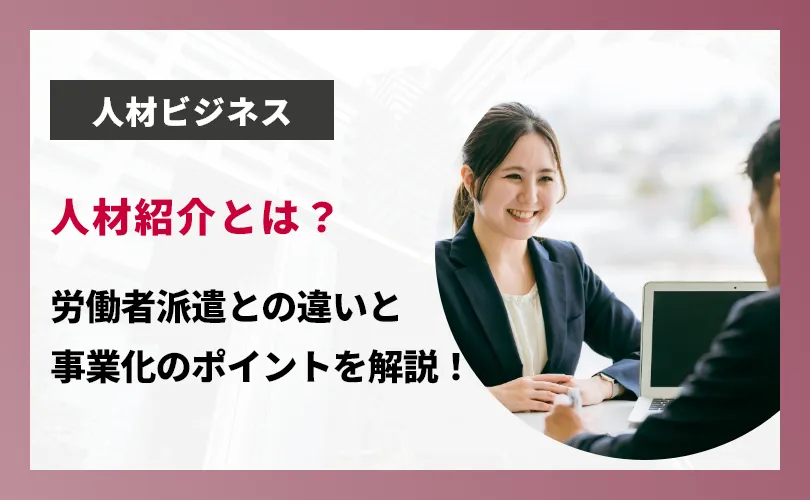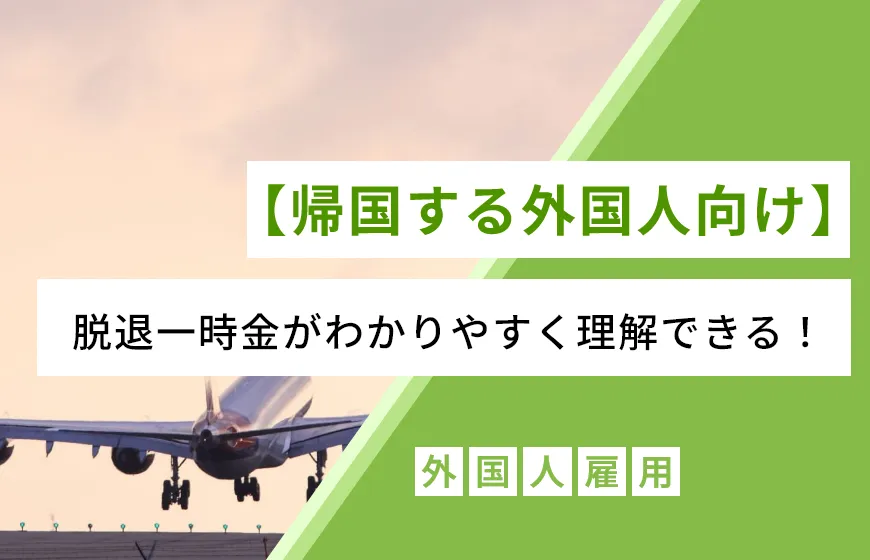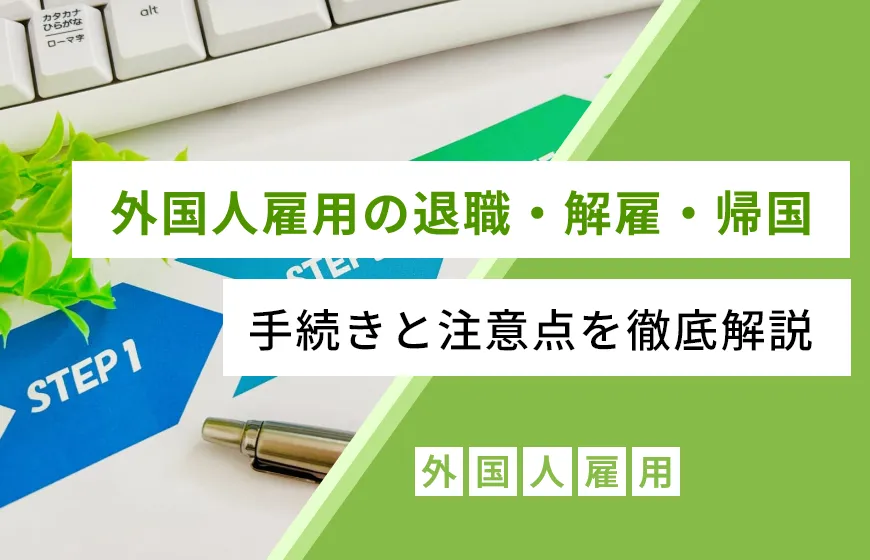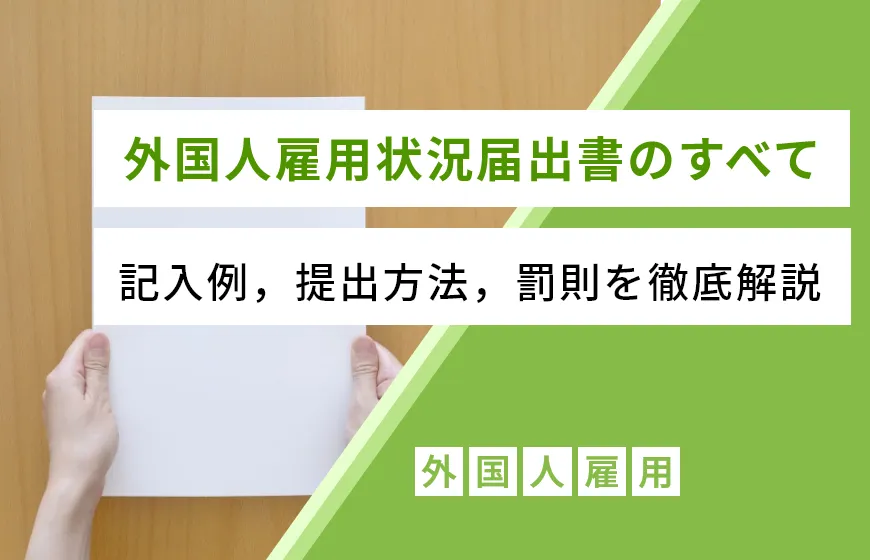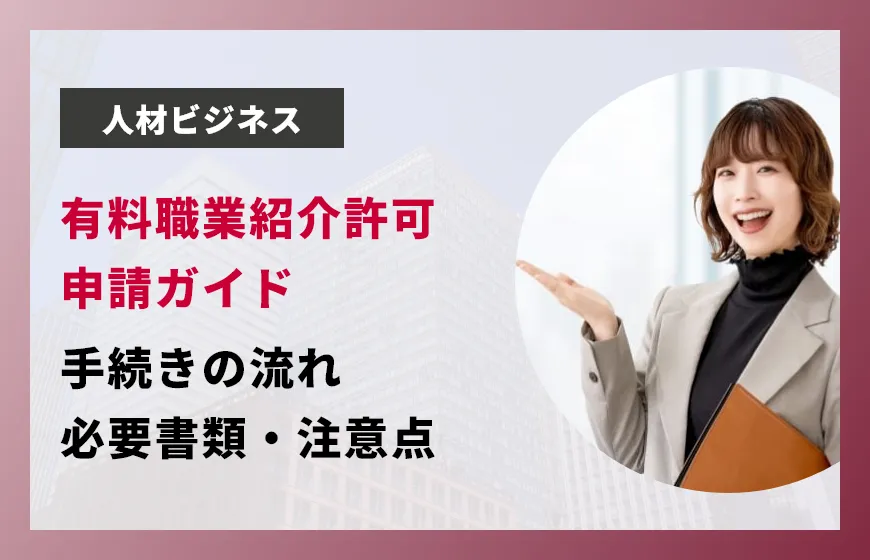
「人材ビジネスを始めたい」「人材紹介業で企業と求職者をつなぎたい」そんな方にとって最初の関門となるのが有料職業紹介事業の「許可申請」です。
実際には,どんな書類が必要なのか,許可申請の流れなど,手続きを進める上で疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは,有料職業紹介の許可を取得するための手続きの流れ,必要書類,審査のポイント,許可後の対応まで,社労士の視点からわかりやすく解説します。
まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!
目次
1.有料職業紹介事業とは?
有料職業紹介事業とは,厚生労働大臣の許可を受けて,求職者と求人者の間に立ち,職業の紹介を行う事業のことを指します。紹介の対価として求人者から手数料を受け取ることができる点が特徴です。
この制度は,単なる人材マッチングにとどまらず,求職者のキャリア形成や就業機会の拡大を支援し,企業の人材確保を円滑にする重要な社会インフラの一つと位置づけられています。また,法令に基づき運営されるため,職業紹介の透明性や公平性が確保されており,健全な雇用市場の形成に寄与しています。
1-1.無料職業紹介事業との違い
有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の最大の違いは,その名の通り,手数料の有無にあります。
無料職業紹介事業では,求職者・求人者のいずれからも手数料を受け取ることはできません。主にハローワークや自治体,学校法人などの公共機関や教育機関がこの形態を採用しており,求職支援の一環として運営されています。
一方で,有料職業紹介事業は,求人者から手数料を受け取ることが可能で,手数料は原則として求職者の就職が成立したタイミングで発生します。金額は求人企業の規模やポジションの内容,年収などによって異なることが一般的です。
有料職業紹介事業の特徴
- 即戦力となる中途人材や専門職,管理職などに特化したものもある
- 非公開求人や独自ルートの求人情報も提供できる
- キャリアコンサルティング等の付加価値サービスを提供しているものもある
一方,無料職業紹介では,新卒や第二新卒を含む幅広い層の求職者を対象とし,地域性や職種の偏りが比較的少ない求人を取り扱う傾向にあります。
このように,紹介手法やターゲット層,提供サービスの内容においても両者には明確な違いがあるため,自社の採用ニーズに応じて適切な制度の理解と選択が必要になります。
2.有料職業紹介事業を行うための許可要件
有料職業紹介事業を始めるには,厚生労働大臣の許可を受ける必要がありますが,その際には複数の厳格な要件をすべて満たさなければなりません。本章では,「資金要件」「情報管理体制」「適格性」「運営体制」の4つの主要な許可要件について解説します。
2-1.資金要件
有料職業紹介の許可を得るには,事業の安定的な運営が可能であることを財務面から証明する必要があります。具体的には以下の2点を1事業所ごとに満たすことが条件となります。
純資産(資産-負債)が500万円以上あること
会社として債務超過の状態ではなく,健全な経営基盤があることを求められます。
設立直後で貸借対照表の実績がない場合でも,出資額や資本金等で証明可能です。
現金または預貯金150万円以上あること
紹介業務の開始直後は売上が立ちにくいため,運転資金として十分な流動性があることが重視されます。
銀行残高証明書(原則3ヶ月以内の発行)が必要です。
この2つの要件は,「許可後すぐに事業が頓挫しないか」という点を見極める審査上のポイントとなっているため設けられています。
2-2.情報管理体制
求職者や求人者の個人情報を取り扱う事業であるため,個人情報保護の観点から厳しい管理体制が求められます。
取扱規程の整備と運用
たとえば,履歴書や職務経歴書の保管方法,アクセス制限,破棄ルールなどを規定します。紙媒体・データ両面での対策が必要です。
収集禁止情報の管理
求職者の能力に応じた職業を紹介するために必要な範囲で求職者の個人情報を収集することとし,思想・信条・本籍などの情報は収集・管理してはいけません。
情報漏洩・苦情対応の体制
万一漏洩やトラブルが起きた際の対応フローや,苦情受付窓口の設置も要件です。マニュアルと実行履歴(教育記録)も確認されます。
2-3.事業主や職業紹介責任者の適格性
申請を行う法人やその代表者,さらに職業紹介責任者となる人には,信用性・経験・資格等の要件が定められています。
欠格事由の非該当
労働基準法,職業安定法,労働者派遣法などに違反して処罰された経験がある場合,内容により6カ月~1年間,申請が不受理となることがあります。
職業紹介責任者の講習受講+経験3年以上
講習は全国で定期的に実施されています。なお,職業経験は「職業紹介に関する実務」ではなく,一般的な職業経験(社会人経験)でOKとされていますが,履歴書や在籍証明書などでの証明が必要です。
2-4.運営体制
事業を行う拠点である「紹介事業所」についても,物理的・制度的な条件が複数定められています。
原則20㎡以上の広さとプライバシー確保
面談ブースの設置や外部からの視線を遮る仕切りがあるかなどが見られます。シェアオフィス利用時は個別ブースや法人契約が求められる場合もあります。
名称に関する制限
「ハローワーク〇〇」「〇〇労働局」など,公的機関と誤認されるような表記は不可です。Webサイトの表現にも注意が必要です。
兼業時の情報区分管理
派遣業と兼業する場合は,求職者の情報や業務担当者を明確に分ける必要があります。同一担当者が両方を兼務する場合は注意が必要です。
手数料表の整備
求人者から徴収する報酬の内容(例:年収の〇%)を明示した書面が必要です。変更時には都度,届出が必要となる場合もあります。
これらの許可要件をすべて満たすことで,有料職業紹介事業の許可を取得することができます。
3.許可申請に必要な書類
有料職業紹介事業の許可を取得するためには,一定の様式に沿った申請書と多くの添付書類を整えたうえで,労働局へ申請を行う必要があります。
提出書類は,申請者が許可要件を満たしているかどうかを判断する重要な審査資料となるため,記載ミスや不備があると審査が長引く,または不許可となることもあります。
ここでは,「申請書類」と「添付書類」に分けて,具体的な提出物の内容と注意点を解説します。
3-1.許可申請書一覧
まず,申請に必要な基本の様式は以下の2点です。
- 有料職業紹介事業許可申請書(正本1部・写し2部)
- 有料職業紹介事業計画書(正本1部・写し2部)
※各都道府県の労働局ホームページからダウンロードが可能です。
計画書には,事業の概要・手数料の取扱い・責任者の配置状況などを詳細に記載します。そして,申請書や計画書の記載内容と,後述する添付書類の内容に矛盾がないことが非常に重要です。
記載に不安がある場合は,事前に労働局への相談や社労士等の専門家への確認をおすすめします。
3-2.添付書類一覧
申請書に加えて,事業主の信用性・資金力・運営体制を証明するための多くの添付書類が必要です。以下に,分類ごとに主な添付書類を紹介します。
法人に関する書類
- 定款または寄附行為(会社の目的に職業紹介事業が含まれている必要あり)
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
代表者・役員・職業紹介責任者に関する書類
- 住民票の写し(本籍地・マイナンバーの記載なし)
- 履歴書(代表者および責任者について)
- 職業紹介責任者講習受講証明書の写し(責任者に限る)
資産および資金に関する書類
- 貸借対照表および損益計算書
- 法人税の納税証明書(その2)
- 株主資本等変動計算書
個人情報の適正管理に関する書類
- 個人情報の適正管理および秘密保持に関する規程(社内規定)
業務の運営に関する書類
- 業務運営に関する規程(求職受付や苦情処理等の対応体制を明記)
事業所施設に関する書類
- 建物の登記事項証明書(自己所有の場合)
- 建物の賃貸借契約書または使用貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所のレイアウト図(面接室・執務室の構造がわかる図面)
手数料に関する書類
- 届出制手数料の届出書(求人者から手数料を徴収する場合)
これらの書類は一部が原本,または原本証明が必要な場合があります。また,取得に時間がかかる書類(例:納税証明書,登記事項証明書)もあるため,余裕を持って準備をしましょう。遅くとも申請予定日の1ヶ月前には準備に着手することを推奨します。
3-3.国外にわたる職業紹介
国外にわたる職業紹介を行う場合には,通常の申請書類に加えて,以下の添付書類が追加で求められます。
※外国人求職者を日本企業へ紹介する場合,または日本人を海外企業へ紹介する場合など
国外紹介に関する書類
- 紹介先との取引契約書(写し)
→ 日本法人と海外企業・機関との間で取り交わした契約書で,紹介業務の内容や手数料,労働条件などが明記されている必要があります。 - 紹介先の会社概要書類
→ 紹介先企業の登記簿謄本に相当する書類や会社パンフレットなど,実在性と業務実態を証明できるものを提出します(日本語訳を添付)。 - 海外の法令に関する説明書
→ 紹介先国における労働法や労働条件,ビザの発給要件などに関する調査資料が求められる場合があります。
翻訳と証明
外国語の書類には,日本語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳文には,翻訳者の署名および翻訳日を明記し,原文との一致を証明してください。
4.許可申請の手順と流れ
有料職業紹介事業の許可申請は,準備すべき書類の多さや審査の複雑さから,計画的な進行が求められる手続きです。
申請前の労働局との相談から始まり,職業紹介責任者の選任・講習,必要書類の作成,提出,そして審査・実地調査を経て,ようやく許可が下ります。
ここでは,申請に至るまでの流れと注意点を順を追って解説します。
4-1.手順①:申請前の相談
有料職業紹介事業の許可申請を円滑に進めるためには,事前に事業主管轄の労働局へ相談することがとても大切です。
労働局では,事前相談を通じて,申請者が許可要件を満たしているかどうかの確認や,書類作成時の注意点について助言を行っています。
特に初めて申請する場合や,制度の詳細に不安がある場合には,事前相談で方向性を確認することで書類の作成や添付書類の収集など,確実に行うことができます。
4-2.手順②:職業紹介責任者の選任と講習の受講
有料職業紹介事業を行うには,職業紹介に従事する者50人につき1人以上の職業紹介責任者を選任し,その者が厚生労働大臣指定の講習を受講済みであることが求められます。
職業紹介責任者とは?
職業紹介責任者とは,苦情対応,個人情報管理,業務の調整などを通じて,紹介業務全体を統括管理する役割を担う人物です。求職者と求人者,双方に対して責任ある対応を行う重要なポジションです。以下のような業務を行います。
- 求職者対応
面談による希望条件・スキルのヒアリング,求人紹介,応募書類作成や面接対策の支援 - 求人企業対応
企業の採用ニーズの把握,求人票の作成・管理,選考の進行サポート - 求人情報の管理
条件に合った求人提供,情報の定期更新・管理,機密保持対応
また,職業紹介責任者となるための講習は各地域で定期的に開催され,修了証明書の写しが申請時に必要です。選任後すぐに受講するようスケジュールを調整しましょう。
4-3.手順③:許可申請書の作成及び提出
申請を行うには,下記の書類を整えて事業主管轄労働局に提出します。提出方法は,窓口持参・郵送・電子申請のいずれかが選択可能です。
提出書類と部数
- 職業紹介事業許可申請書および事業計画書:各3部(正本1部・写し2部)
- 添付書類:2部(正本1部・写し1部)
提出時期の目安
- 申請は,事業開始希望日の3~4ヶ月前までに行うのが一般的であり,余裕を持ったスケジュール管理が望ましいです。
記載内容に不備があると,再提出が必要になったり,許可が予定より遅れるケースもあるため,事前相談の内容を反映して丁寧に準備することが重要です。
4-4.手順④:審査と許可
申請後,労働局による審査が行われ,通常2~3ヶ月程度の期間を要します。この間,追加書類の提出依頼や,事業所の実地調査が行われるのが一般的です。
実地調査の内容(例)
- 面談スペースの有無やプライバシー確保状況の確認
- 個人情報管理(書類・PC)の実態確認
- 職業紹介責任者との面談や体制確認
調査結果や追加対応に時間がかかると,許可の取得時期が遅れることもあります。
なお,許可日は毎月1日付で発効されるため,たとえば6月1日付の許可を目指す場合,4月初旬には申請を終えておく必要があります。
申請手続きは複雑かつ専門的な要素が多いため,不安がある場合やスケジュールに余裕がない場合は,社労士などの専門家への相談をおすすめします。
的確なアドバイスを得ることで,書類の不備や手続きの遅延リスクを大幅に減らし円滑に申請を進めることが可能となります。
5.許可後の手続き
有料職業紹介事業の許可を取得した後も,事業者としての法的義務は継続的に発生します。
事業を安定的に運営し続けるためには,変更事項の届出や定期報告といった管理業務を適切に行うことが求められています。ここでは,許可後に必要な主要手続きを紹介します。
5-1.変更届
許可取得後,以下のような事項に変更があった場合は,変更後30日以内に管轄労働局へ変更届を提出しなければなりません。
届出が必要な主な変更内容
- 事業所の名称や所在地の変更
- 代表者,役員,職業紹介責任者の変更
- 連絡先,事業計画に関する重要事項の変更 など
また,変更届の提出の際には,変更内容を証明する書類の添付が必須です。
添付書類の一例
- 法人の登記事項証明書(代表者や所在地変更時)
- 賃貸借契約書(新事務所への移転時)
- 職業紹介責任者の講習修了証・履歴書(責任者交代時)
届出を怠ると,行政指導や最悪の場合は許可取り消しの対象になる可能性もあるため,変更があった場合は速やかに手続きを行いましょう。
5-2.事業報告書の提出
有料職業紹介事業を行っている場合,毎年1回,「事業報告書」を作成して提出する義務があります。
| 対象期間 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
| 提出期限 | 毎年4月30日まで |
事業報告書には,求職者・求人者の件数,紹介の実績,手数料の徴収状況などを記載する必要があります。取扱実績が「ゼロ」の場合でも,提出は必須ですので注意しましょう。
労働局への提出がない,または期限を過ぎた場合,監督指導の対象となる可能性もあるため,毎年の必ず行う業務として社内でスケジュール管理を徹底することが重要です。
6.許可更新の手続き
有料職業紹介事業の許可は永久に有効なものではなく,一定期間ごとに更新手続きが必要です。
許可の有効期間が満了する前に,適切な時期に必要書類を提出し,更新申請を行わなければ,事業の継続ができなくなるため,注意が必要です。ここでは,許可の有効期間と,更新手続きの具体的な流れについて解説します。
6-1.許可の有効期間
有料職業紹介事業における許可の有効期間は以下の通りです。
- 新規許可 → 3年間
- 更新後の許可 → 5年間
有料職業紹介事業を初めて取得した場合は3年ごと,その後は5年ごとに更新申請が必要となります。
※満了の「翌日から」新たな有効期間が起算されるため,事業継続に空白が生じないよう,期限管理が非常に重要です。
6-2.更新手続きの流れ
更新手続きは,以下のような流れに沿って進められます。
(1)更新申請書の提出
- 提出期限:有効期間満了の3ヶ月前まで
- 提出先:管轄の労働局(事業主管轄)
この期限を過ぎると,いかなる理由があっても更新できません。更新申請のタイミングを逃すと,新たに一から許可申請をし直す必要があるため,スケジュール管理を徹底しましょう。
(2)添付書類の提出
更新申請には,下記のような最新の経営・体制に関する資料の提出が必要です。
- 貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書(最新の事業年度)
- 法人税の納税申告書・納税証明書
- 職業紹介責任者講習受講証明書(前回から5年以内の受講が必要)
※以下のような変更があった場合は追加書類が求められます。
例①:職業紹介事業の目的が明記されていない場合,または改定があった場合
・定款
例②:代表者や所在地の変更などがあった場合
・法人の登記事項証明書
(3)審査
労働局による審査では,以下の点が確認されます。
- 過去の事業運営状況
- 法令違反や行政処分の有無
- 財務の健全性や情報管理体制の維持
必要に応じて,補足資料の提出や実地調査が行われる場合もあります。
(4)許可の更新
審査の結果,引き続き許可要件を満たしていると判断された場合は,更新許可証が交付され,事業を継続することができます。
更新後の許可証は,有効期間満了日の翌日から5年間有効です。
有料職業紹介事業の運営や更新手続きに関して,不明な点がある場合や,書類準備に不安がある場合は,早めに管轄の労働局に相談するか,社労士など専門家のサポートを受けることが重要です。
7.よくあるご質問
ここでは,有料職業紹介事業の申請・運営にあたって寄せられるよくある質問とその回答をまとめました。
Q:有料職業紹介事業において取扱いが禁止されている職業はありますか?
A: はい,以下のような職業については,法令により紹介が禁止されています。
- 港湾運送業務に就く職業
港湾労働法に基づく登録制度があるため - 建設業務に就く職業
労働者派遣との混同を避けるため
これらの業務に関しては,有料職業紹介として取り扱うことはできませんので注意が必要です。
Q:許可申請に必要な費用はどのくらいですか?
A: 主に以下の費用が発生します。
- 登録免許税:90,000円
- 収入印紙代:50,000円
※1事業所あたり必要です。事業所が追加されるごとに18,000円加算されます。
登録免許税の納付書は,都道府県労働局にて配布されます。その他,登記事項証明書や納税証明書の取得費用も別途必要となります。
Q:職業紹介責任者講習はどこで受講できますか?
A: 厚生労働大臣が指定する講習機関での受講が必要です。
- 開催情報や講習スケジュールは厚生労働省のホームページで確認できます。
- オンライン開催にも対応しており,地域によっては対面講習も選べます。
- 講習修了証明書は「理解度確認試験の合格」が条件となっているため,受講後に簡易テストが実施される点にも注意が必要です。
Q:許可更新の手続きを忘れてしまった場合,どうすればいいですか?
A: 許可の有効期限を過ぎてしまった場合は,更新はできません。
その場合は,新規許可申請として一から申請をやり直す必要があります。
業務を継続したい場合は,速やかに管轄の労働局へ相談し,再申請の手続きに入ってください。
Q:許可を取得した後,事業を廃止する場合はどうすればよいですか?
A: 有料職業紹介事業を廃止する際には,廃止後10日以内に以下の手続きを行う必要があります。
- 有料職業紹介事業変更届出書の提出
- 事業所の許可証の返納
事業所が複数ある場合は,廃止対象の事業所を明確に記載する必要があります。
Q:法改正によって,許可申請の内容が変更されることはありますか?
A: はい,職業安定法や関連省令の改正により,許可基準や運営ルールが変更される場合があります。たとえば,2025年1月からは以下の規定が新たに追加されています。
- 「紹介により就職した日から2年間,転職勧奨の禁止」
- 「お祝い金や紹介特典などの提供の禁止」
許可申請時や更新時には,必ず最新の法令・通達を確認し,制度変更に対応することが求められます。
Q:副業紹介を目的とした有料職業紹介も可能ですか?
A: 副業・兼業を対象とした紹介も可能ですが,労働時間や社会保険の適用関係,雇用契約の内容などが複雑になるため,求人内容や求職者への説明には十分注意が必要です。
また,紹介先企業の就業規則や副業許可の有無も確認してから進めるのが望ましいです。
Q:外国人の紹介もできますか?
A: 原則として可能です。
ただし,外国人の場合は在留資格(就労資格)の内容を確認し,適法な範囲で紹介を行う必要があります。
たとえば,留学生や技能実習生には紹介できないケースがあるため,在留カードの確認や,受け入れ企業の受入体制の適格性も重要です。
8.まとめ
本コラムでは,「有料職業紹介事業の許可申請」に関する全体像を,申請の流れ・必要書類・許可要件・許可後の管理・更新手続き・よくある質問を解説しました。
有料職業紹介事業は,人材を紹介するだけでなく,求職者のキャリア形成と企業の成長を同時に支援する社会的に重要な事業です。その一方で,法令に基づく許可制であるため,許可申請や届出の流れ,書類整備,運営体制など,細かな手続きや継続的な管理が必要となります。
もし,「何から始めたらいいかわからない」「申請に不安がある」「更新期限が迫っている」といったお悩みがあれば,どうぞお気軽にご相談ください。
弊社,社会保険労務士法人第一綜合事務所では,許可申請から許可後の運営支援までサポートしております。有料職業紹介事業許可について知りたいことがあれば,お気軽に無料相談をご利用ください。
この記事の監修者
社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛
- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)
東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。