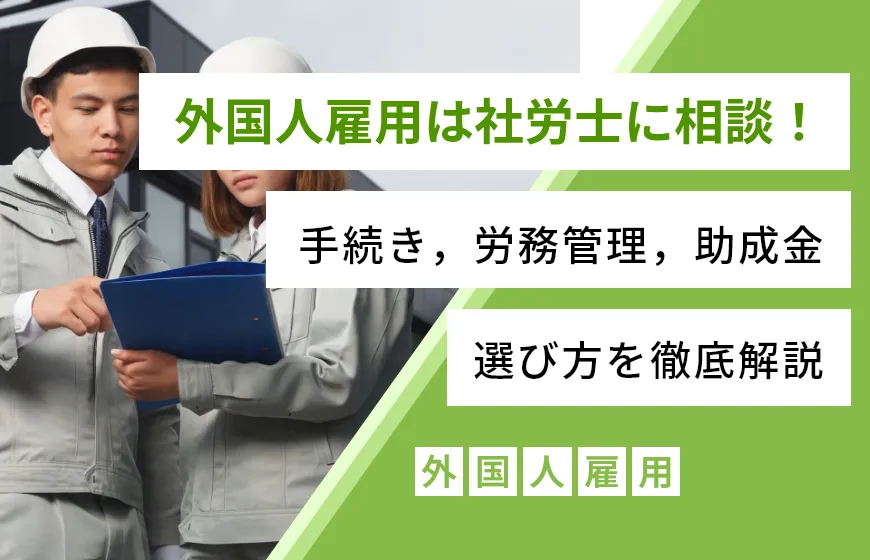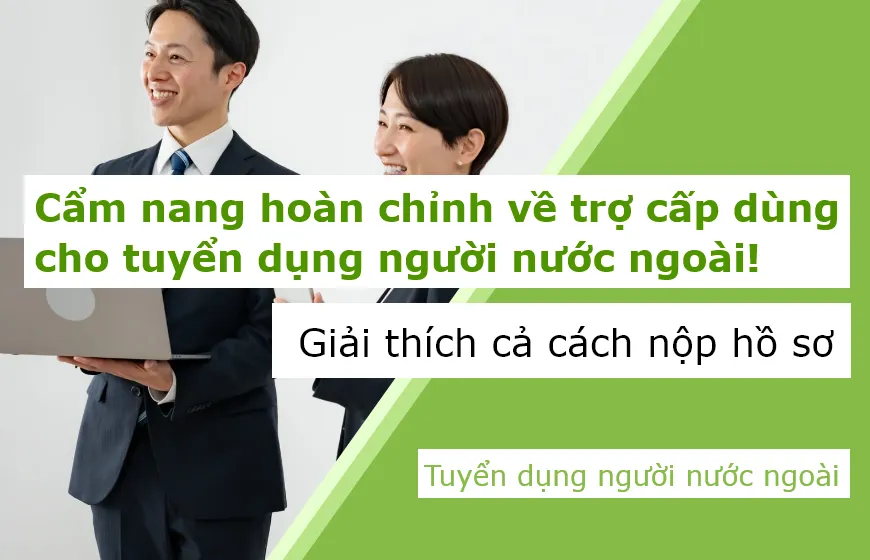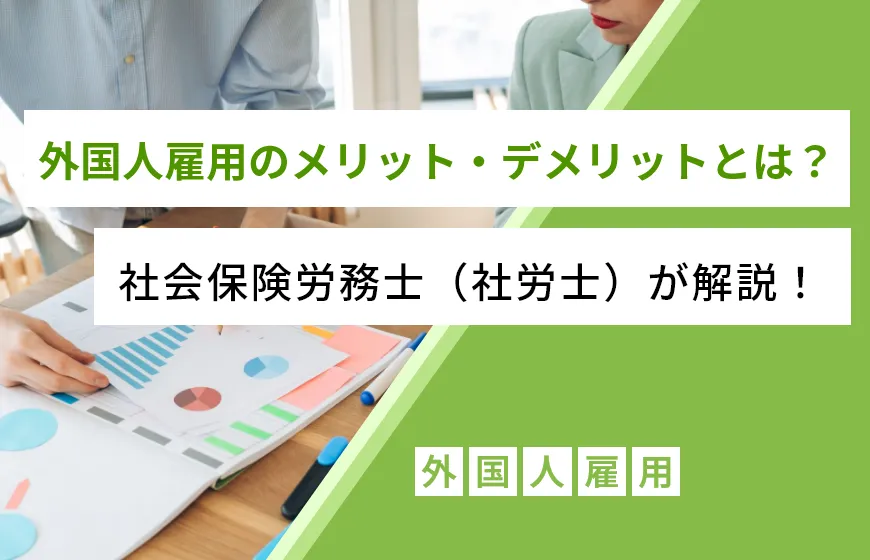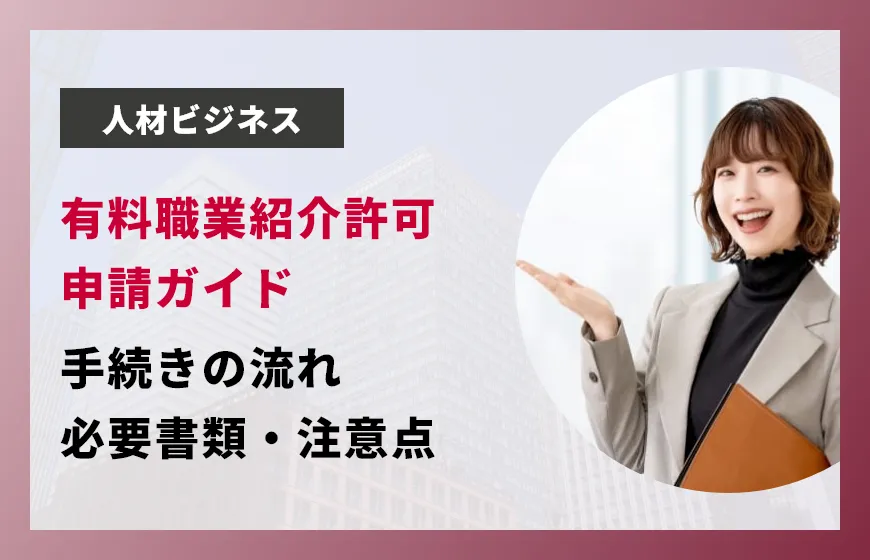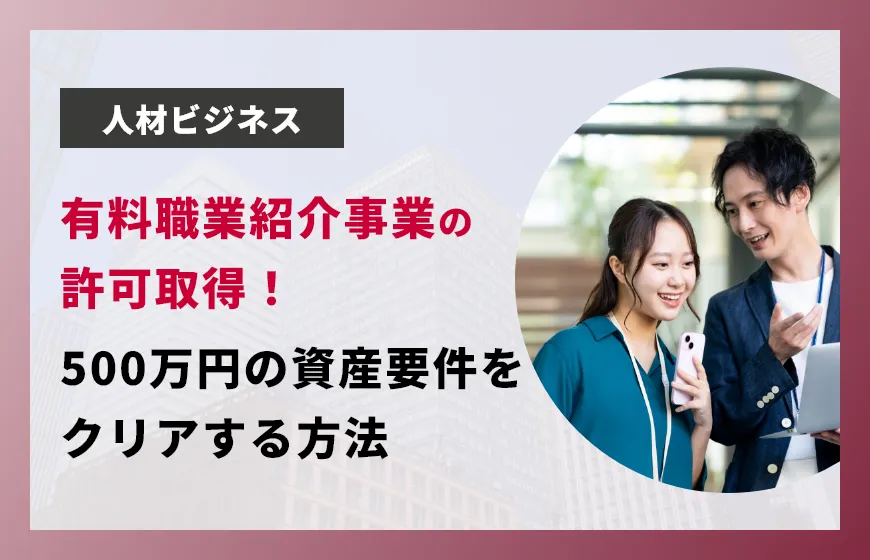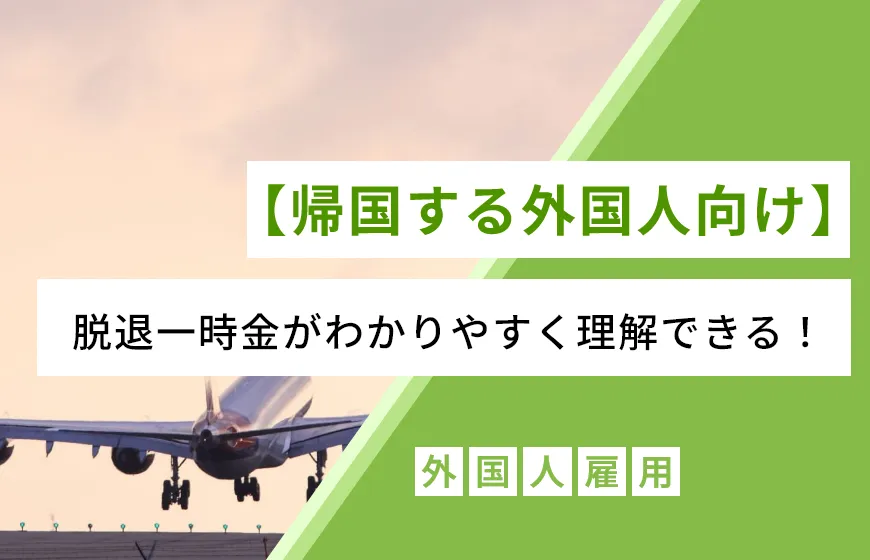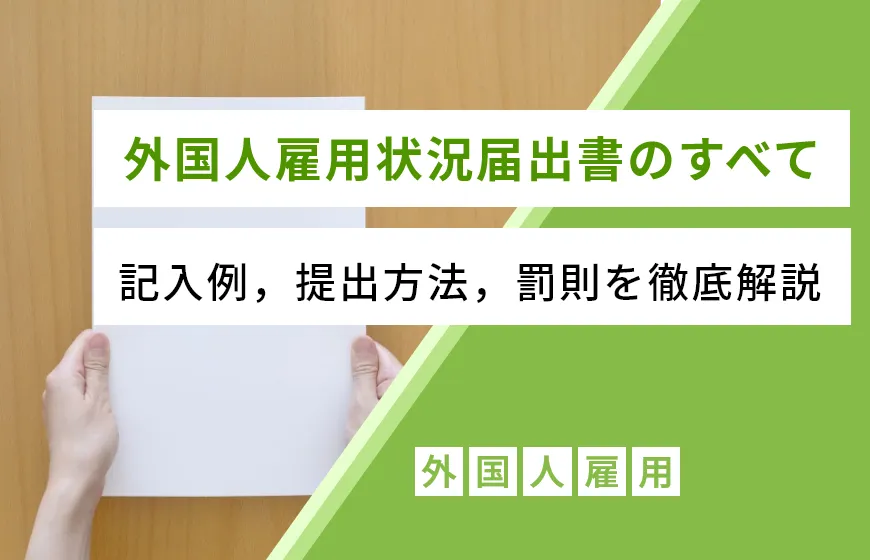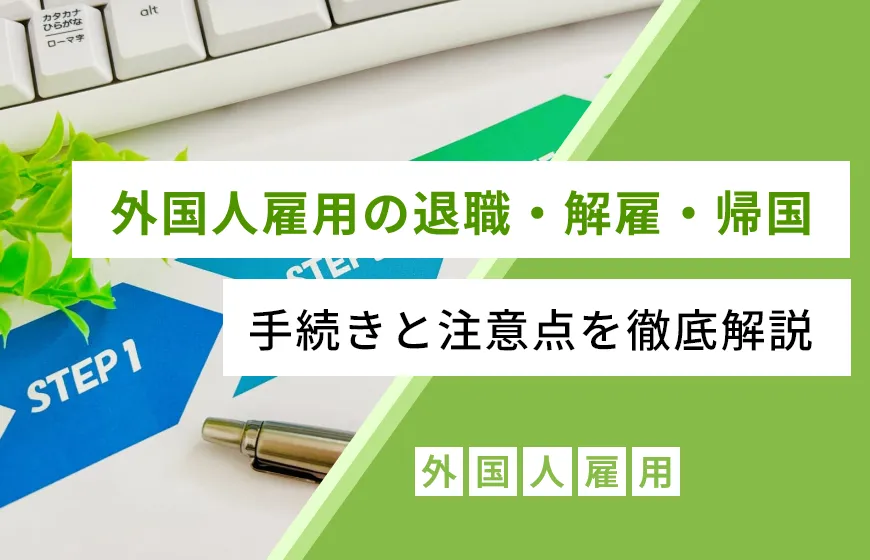外国人を雇用する企業にとって「助成金の活用」は採用コストを抑えつつ,安定した雇用環境を整えるチャンスです。しかし,制度の種類が多く,どれが自社に合っているのか分かりにくいと感じていませんか?本コラムでは,外国人雇用に活用できる代表的な助成金を厳選し,それぞれの特徴や活用ポイント,申請方法まで,社労士の視点からわかりやすく解説します。
人材確保等支援助成金,キャリアアップ助成金,人材開発支援助成金など,実務で役立つ情報をまとめてお届けしますので,ぜひ最後までご覧ください。
まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!
目次
1.外国人雇用で利用できる助成金とは?
外国人を雇用する際,国の助成金制度をうまく活用することで,採用コストを抑えながら,より良い雇用環境を整えることが可能です。
この章では,外国人雇用に関連する代表的な助成金の概要と,その意義について解説します。
1-1.助成金活用のメリット
外国人労働者の採用・育成には,日本人と異なる配慮やコストが必要となることも少なくありません。そこで活用したいのが,企業を支援するために設けられた各種助成金制度です。
助成金の最大の魅力は,「費用の一部を国が負担してくれること」です。外国人労働者を雇用する際には,研修・制度整備・雇用管理などに追加コストが発生することがありますが,それらの一部を助成金でカバーすることで,企業の経済的負担を軽減することができます。
助成金活用のメリット
人材育成コストの軽減
資格取得や業務スキル研修などにかかる費用の一部を国が補助します。教育投資への心理的ハードルが下がり,人材育成が進みやすくなります。
制度整備に伴う初期コストを補助
マニュアル作成や通訳導入,多言語対応など,外国人雇用に伴う環境整備の初期投資も助成対象になります。整備を後回しにせず,早期に着手する動機づけとなります。
雇用継続・定着の仕組み作りに必要な費用を支援
定着支援に関わる活動(相談窓口の設置など)も対象になり,離職リスクを抑える施策を具体的に打ち出しやすくなります。
これらの制度を通じて,環境整備を行うことで外国人労働者だけでなく日本人従業員にとっても働きやすい職場へと進化し,組織全体の生産性や定着率向上につながります。
2.各助成金の詳細解説
外国人雇用に活用できる助成金には,目的や対象となる取り組みに応じて,様々な種類があります。どの助成金が自社に適しているのかを見極めるためにも,制度の概要と支給要件を確認しておきましょう。
紹介する助成金
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- キャリアアップ助成金
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
- その他の助成金
2-1.人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者は,日本の労働法制や雇用慣行に関する知識の不足,言語の壁などから,労働条件や解雇をめぐるトラブルが生じやすい傾向があります。
この助成金は,外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備に取り組む事業主に対し,その経費の一部を助成する制度です。主な支給対象経費は以下のとおりです。
- 通訳費
- 翻訳機械導入費
面談に必要な翻訳機器の導入に限ります。 - 翻訳料
社内マニュアルや標識類などの多言語対応にかかる費用。 - 専門家への委託料
弁護士や社会保険労務士等への労働契約書作成・見直し,職場環境改善の相談料。ただし,顧問契約や定期的な相談料など継続的な支払いは対象外です。 - 内標識の設置・改修費
多言語表示の社内標識を外部に依頼して設置・改修する場合に限られます。
本助成金を受給するためには,以下の「必須要件」をすべて満たす必要があります。加えて,「導入対象となる制度例」のいずれかを導入・実施する必要があります。
必須要件
- 外国人労働者との定期面談の実施
- 就業規則の多言語化
導入対象となる制度例
※下記のいずれかの制度を1つ以上導入・実施することで,1制度につき20万円,最大4制度・上限80万円までの助成を受けることが可能です。
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の導入
- 社内マニュアルや標識類の多言語化
- 生活支援担当者の配置
- 日本語教育の提供体制整備 など
※導入可能な制度の選択肢は複数あり,組み合わせによって助成額が変動します。
上記制度を導入した場合,1制度につき20万円(最大4制度,上限80万円)の助成を受けることができます。
引用:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
2-2.キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は,有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者といった非正規雇用者のキャリアアップを支援する制度です。こちらは日本人だけでなく,外国人労働者にも適用され,処遇の改善や雇用の安定,キャリア形成を図ることができます。
代表的なコースは以下のとおりです。
| コース名 | 内容 | 支給額(中小企業の場合) |
|---|---|---|
| 正社員化コース | 有期契約労働者を正社員に転換した場合 | 1人あたり 最大80万円※中小企業以外は最大60万円 |
| 賃金規定等改定コース | 基本給を3%以上引き上げた場合 | 1人あたり 最大7万円※中小企業以外は4.6万円 |
| 賃金規定等共通化コース | 正規雇用者と同様の賃金規定を非正規雇用者にも適用 | 1事業所あたり 最大60万円※中小企業以外は45万円 |
| 賞与・退職金制度導入コース | 賞与・退職金制度を新たに導入・実施 | 1事業所あたり 最大56.8万円※中小企業以外は42.6万円 |
| 社会保険適用時処遇改善コース | 社会保険適用と同時に処遇(収入)を改善した場合 | 1人あたり 最大50万円※中小企業以外は37.5万円 |
これらの制度を活用することで,外国人労働者を正社員に転換する際の経済的負担を軽減することが可能になります。また,労働者側のメリットとして,処遇改善によりモチベーションや生産性の向上にもつながります。
2-3.人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金は,企業が雇用する労働者に対して,業務に必要な専門知識や技能の習得を目的として職業訓練を実施した場合に,その訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。
中でも「人材育成支援コース」は,正社員化やスキル高度化を目的としたOFF-JTやOJT(一定の要件を満たすもの)を計画的に実施する必要があります。
助成対象となる訓練は,あくまで業務に直結した内容であることが求められ,一般的な教養研修や業務との関連性が乏しい内容は対象外となります。
例えば,外国人労働者に対しては以下のような訓練が助成対象となりやすい内容と言えます。
資格取得
職務に必要なビジネス日本語,接客用語,安全衛生用語など(一般的な語学学習では対象外)
業務スキル研修
具体的な業務で使用するITスキル(例:Excel実務,POSレジ操作など),介護技術,接客マナー,業務マニュアルに基づいた操作研修 など
訓練時間はOFF-JTで10時間以上,またはOJTと組み合わせた訓練(有期契約労働者の正社員転換を目的としたもの)である必要があります。
| 区分 | 中小企業事業の定義 | 訓練経費助成率 | 賃金助成額(上限) |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 製造業 資本金3億円以下 常時使用労働者300人以下 卸売業 資本金1億円以下 常時使用労働者100人以下 サービス業 資本金5,000万円以下 常時使用労働者100人以下 小売業 資本金5,000万円以下 常時使用労働者50人以下 | 45~85% | 1人1時間あたり 最大800~1,000円円 |
| 大企業(中小企業以外) | 上記以外の企業 | 30~85% | 1人1時間あたり 最大400~500円 |
2-4.その他の助成金
上記以外にも,外国人雇用に活用できる助成金があります。以下に代表的な制度を紹介します。
両立支援等助成金
育児や介護と仕事を両立できる職場環境を整備した場合に支給されます。外国人労働者の家庭事情に対応する制度構築に活用できます。
トライアル雇用助成金
職業経験が少ない求職者を試行的に雇用する場合に支給されます。外国人を試行的に雇用する際に利用可能です。
特定求職者雇用開発助成金
高齢者や障害者など,就職困難者を雇用した場合に支給されます。外国人労働者の中でも特定条件に該当する場合に対象となります。
それぞれの助成金には要件や支給額に違いがあるため,自社の課題や雇用管理に合わせて最適な制度を選定することが大切です。
3.助成金の申請方法
助成金の申請には,計画の立案から実施・報告まで,いくつかの流れがあります。また,申請に必要な書類や注意点も多いため,あらかじめ全体の流れを把握し,抜け漏れのないように準備を進めることが大切です。
ここでは,外国人雇用に関連する助成金の申請手順,必要書類,注意点について詳しく解説します。
3-1.申請の流れ
助成金の申請手続きは,以下の流れで進みます。
①計画書の作成・提出
助成金の支給要件として事前に訓練や就労環境整備の実施計画書を作成し,都道府県労働局へ提出します。
②申請書類の準備
助成金ごとに申請書類が定められていますので確認し,必要書類を作成しましょう。不備が無いように事前に準備しましょう。
③計画の実施
訓練や就労環境整備の実施を行います。
計画の内容と相違する場合には,助成金が不支給となる可能性があるので,計画通りに実行しましょう。
④申請書類の提出
定められた支給申請期間に準備した申請書類を都道府県労働局へ提出します。郵送または電子申請で提出できます。電子申請を行うにはあらかじめGビズIDの取得が必要となります。
※GビズIDとは…
すべての事業者を対象とした共通認証システムです。
アカウントを作成すると,一つのID・パスワードで,複数の行政サービス にログインでき,補助金申請,社会保険手続,各種認可申請など業務上の電子届出や申請に使用できます。
ID発行時に一度だけ代表者の身元確認を行えば,その後の各手続での本人確認書類提出が不要になります。
アカウントは 最初に1つ 取得するだけで, 有効期限,年度更新の必要はありません 。
⑤審査と支給決定
通常,6カ月以上の審査期間が見込まれます。
3-2.必要書類
助成金の申請には様々な書類が必要です。これらの書類は助成金の種類や申請内容によって異なりますが,一般的なものとしては以下のものが挙げられます。
申請書
助成金の申請を行うための書類です。厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。
雇用契約書
外国人労働者との雇用契約の内容を証明する書類です。労働条件や給与などが記載されています。
就業規則
企業の就業規則を提出します。外国人労働者の労働条件に関する規定が含まれているかを確認されます。
賃金台帳
外国人労働者の賃金支払いの記録を証明する書類です。給与や社会保険料などが記載されています。
出勤簿(勤怠記録)
実際の勤務実績を確認するための書類で,訓練期間中の出勤状況を証明するために必要です。
その他
企業の登記簿謄本,訓練の受講案内や経費に係る請求書及び領収書の写しなどがあります。
提出書類のうち,不足している書類があると,申請が受理されない場合や支給決定までに通常以上に時間を要するため,注意が必要です。
書類の作成や収集に不安のある方は,社労士などの専門家と連携したり,管轄の労働局に問い合わせをしてみることをおすすめいたします。
3-3.注意点
助成金の申請にあたってはいくつかの注意点があるため,ご紹介します。
申請期間の厳守
助成金には申請期間が定められています。申請期間を過ぎてしまうと申請を受け付けてもらえません。申請期間を事前に確認し,余裕をもって申請書類を準備しましょう。
申請要件の確認
助成金には様々な申請要件があります。自社がこれらの要件を満たしているか,事前に確認しておく必要があります。要件を満たしていない場合は,申請を行っても助成金の支給を受けることができません。
不正受給の禁止
虚偽の申請や不正な手段による助成金受給は罰金の対象となります。不正受給が発覚した場合,以下のような非常に重い処分や制裁を受ける可能性があります。
- 受給額の全額返還
- 受給額の20%相当の加算金の支払い
- 5年間の助成金受給停止措置
- 事業者名の公表
- 刑事罰(詐欺罪等)の対象となる場合あり
- 企業としての社会的信用の失墜・取引停止リスク
助成金は「正しく活用する」ことが大前提です。事業者として適正な運用を徹底し,社内でもコンプライアンス意識を高めておきましょう。
4.まとめ
外国人雇用における助成金について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。助成金を活用することで,採用コストを抑え,企業の負担を軽減することができます。
このコラムが,外国人雇用を検討している企業の皆様にとってお役に立てれば幸いです。助成金を活用して,ぜひ外国人雇用の成功を実現しましょう。
なお,各種助成金に関して,社会保険労務士法人第一綜合事務所でもご相談を受けております。ご相談をいただいた際には当社スタッフ一丸となって対応をさせていただきます。
この記事の監修者
社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛
- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)
東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。