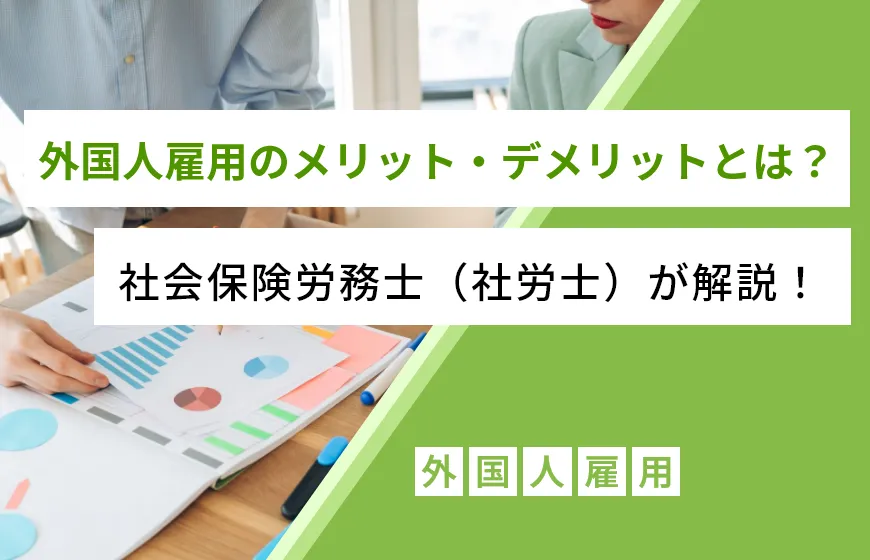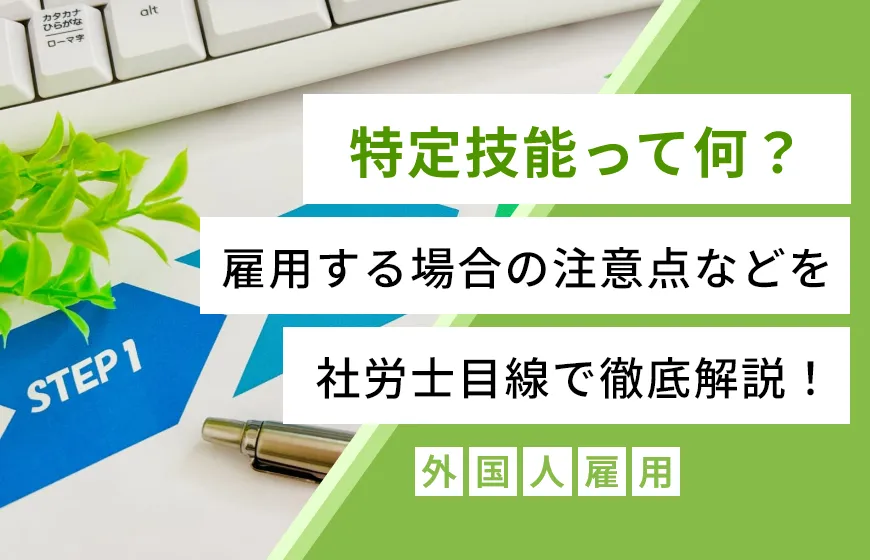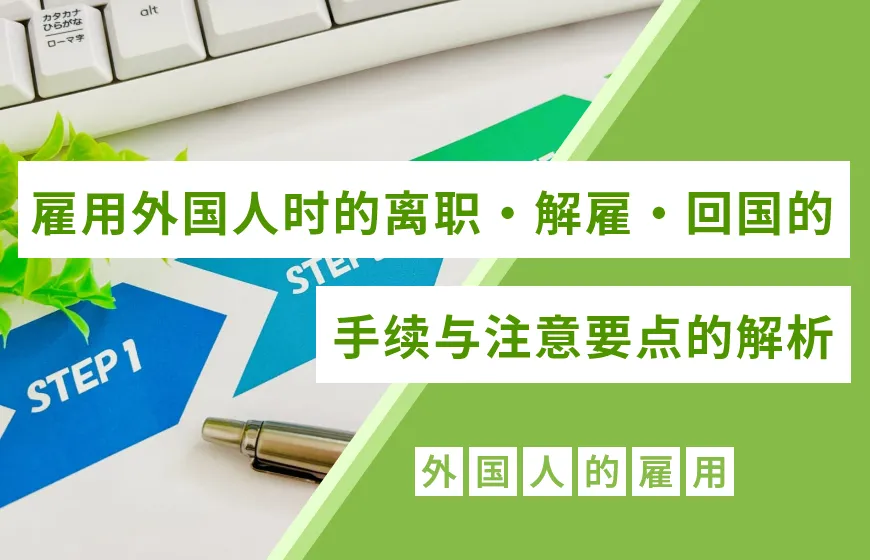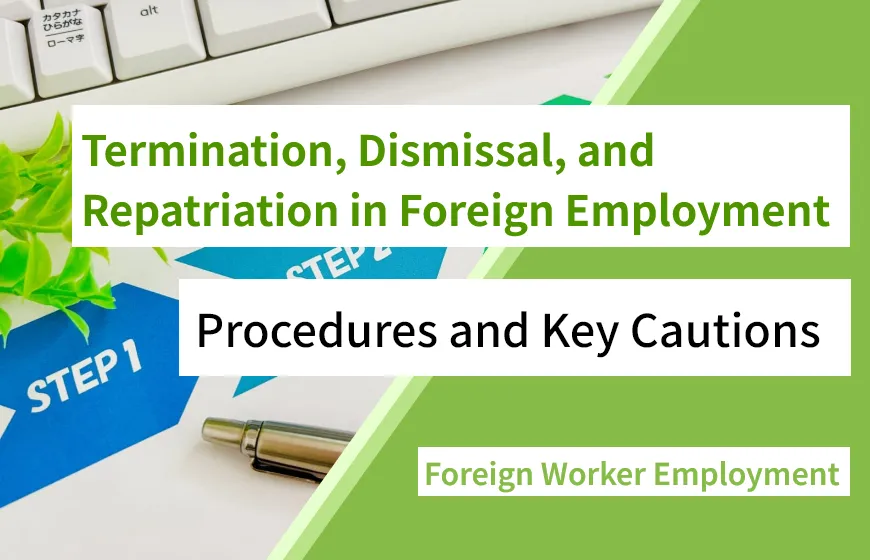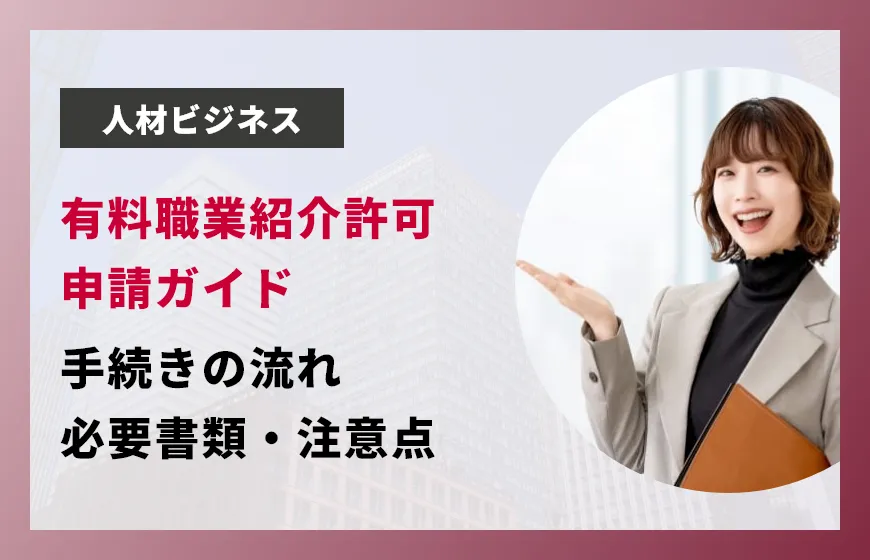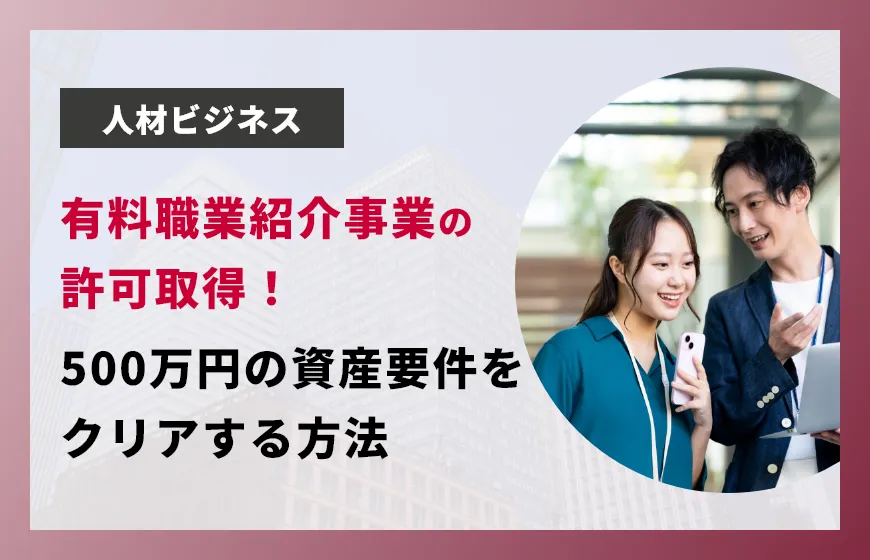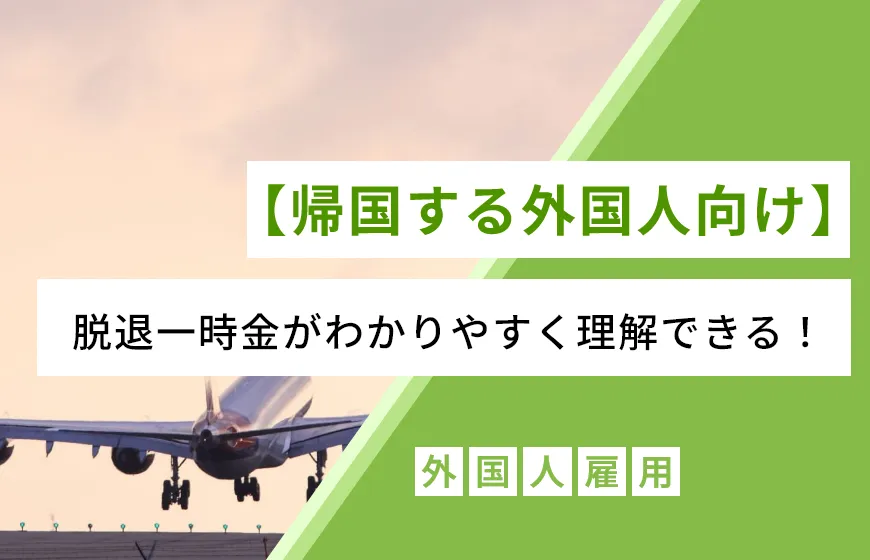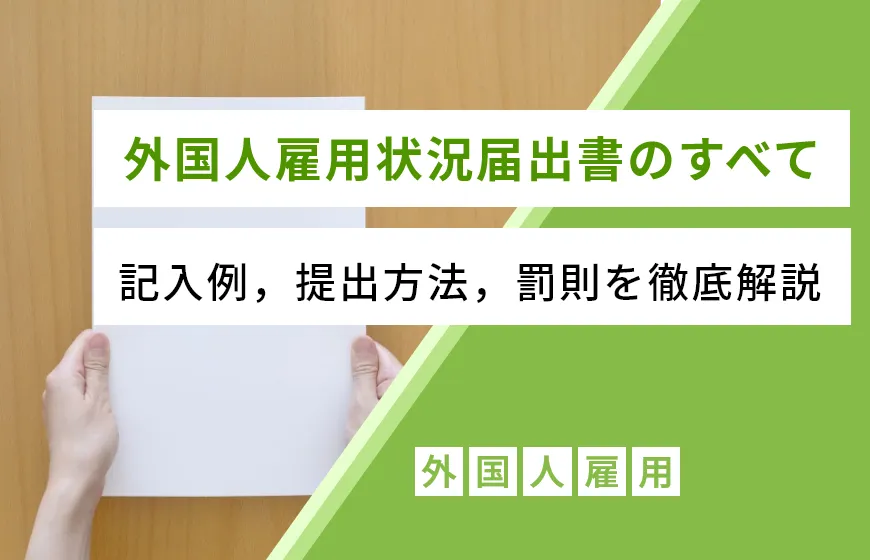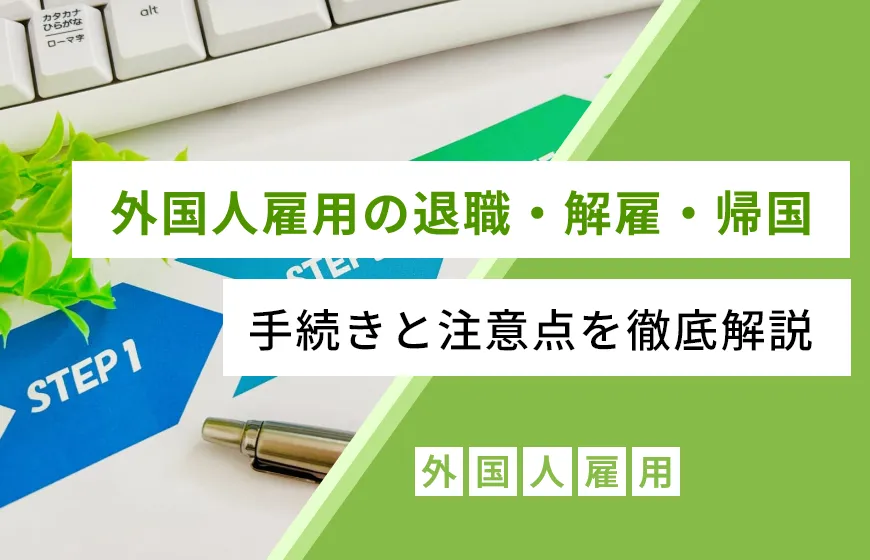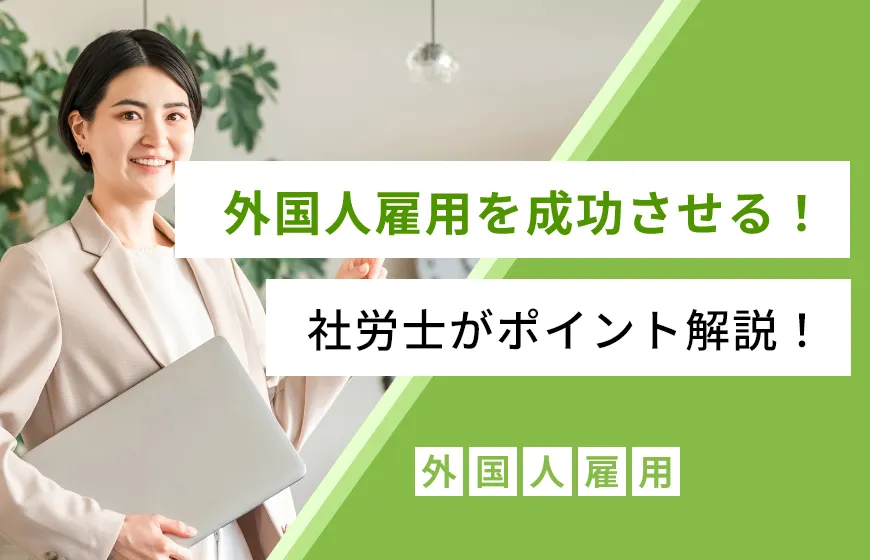
人手不足が深刻化する中,外国人労働者の雇用を検討している企業が増えています。しかし,外国人雇用には,複雑な手続きや法律,文化の違いなど,様々な課題が伴います。「何から始めれば良いのか分からない」「トラブルが心配」と感じている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。本コラムでは,外国人雇用を成功させるために,社労士が提供するサポート内容や,法律,そして失敗しないためのポイントを分かりやすく解説します!
まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!
目次
1.なぜ今,外国人雇用なのか?メリットとデメリットを解説
多くの企業が外国人雇用という選択をとっていますが,外国人雇用にはメリットだけでなく,デメリットも存在します。メリットとデメリットを比較検討することで,自社にとって外国人雇用が最適な選択肢であるかを判断しましょう。
1-1.外国人雇用によるメリット
外国人雇用には,企業にとって多くの利点があります。特に,以下のようなメリットが期待できます。
労働力不足の解消
深刻化する人手不足を補い,事業の継続と発展を支える即戦力として活躍が期待できます。
多様性の創出
異なる価値観や文化を持つ人材が加わることで,組織内に新たな視点が生まれ,イノベーションの促進にもつながります。
グローバル展開の加速
海外ビジネスの拡大やインバウンド対応など,国際的な感覚を持つ人材の活用が企業の成長を後押しします。
1-2.外国人雇用によるデメリット
上記のようなメリットがある一方で,外国人雇用には注意すべき課題もあります。下記のようなデメリットを理解しておけば,事前に対策を講じることが可能となります。
コミュニケーションの壁
言語や文化の違いにより,意思疎通に時間がかかることがあり,当事者間・社内での業務効率に影響する可能性があります。
労務管理の複雑化
在留資格の管理や更新,労働時間・社会保険の手続きなど,通常よりも煩雑な管理業務が求められます。
教育・研修コストの増加
日本語教育や,日本独自のビジネスマナー・労働文化に関する研修が必要になるケースがあります。
法令違反のリスク
永住者や日本人の配偶者など一部の外国人以外は,基本的に就労活動が制限されています。そのことを知らずに法定外の業務に従事させてしまい,不法就労となるリスクがあります。
1-3.メリットとデメリットのバランスを取るために
外国人雇用を成功に導くためには,メリットを活かしつつ,デメリットを最小限に抑える体制づくりを行う視点が必要です。そのために,以下のような事前準備をご紹介します。
- 日本語教育や異文化研修の実施
- 多言語での社内資料整備やサポート体制の構築
- 外国人雇用に詳しい社労士や行政書士への相談
これらの対策を講じ,外国人スタッフが安心して働ける環境を整えましょう。また,自社内の状況や業種により対応できる対策も多種多様ですので,不安がある場合は,社労士などの専門家に相談してみましょう。
2.外国人雇用で必要な手続きと,社労士のサポート内容
外国人雇用を成功させるためには,労働条件の整備や労務管理,社会保険・労働保険の手続きといった多岐にわたる対応が必要になります。この章では,外国人雇用に関する主要な手続きと,それを支援する社労士の役割について解説します。
2-1.労働条件の整備
外国人労働者の雇用にあたっては,日本の労働基準法が外国人労働者にも適用されます。明確かつ公平な労働条件の整備を行う必要がありますが,言語や文化の違いによる誤解を防ぐためにも,以下のような取り組みが重要です。
① 労働契約書の作成と言語対応
外国人労働者と契約を結ぶ際には「労働条件通知書(労基法15条)」または「労働契約書」の作成が義務となりますが,外国人雇用の視点では必ずしも日本語での説明だけでは十分とはいえません。確実に意思疎通をはかるために,以下の対応が望ましいです。
- 労働契約書・労働条件通知書の多言語化(母国語・英語など)を行う
- 専門用語や法的表現を平易な表現に言い換え,やさしい日本語を併用する
- 契約内容の説明時には,通訳や通訳アプリの活用も行う
※弊社では,多言語対応が可能なため,これら多言語契約書の雛形整備,記載内容の法令適合性チェック,外国語版と日本語版の整合性確認までを担うことができます。
② 就業規則の整備・改定
常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成が義務付けられています。外国人雇用がある場合は,以下の観点で特別な配慮が必要です。
- 外国人労働者向けの特則を盛り込む(例:宗教的配慮,食文化対応など)
- 特定技能・留学生アルバイト・高度人材など在留資格別の就労形態に即した規定を用意する
- 労働時間や休暇制度に関する誤解を招かない表現への修正を行う
※社労士は,企業の現状をヒアリングしたうえで,必要に応じた就業規則の新規作成・見直しをサポートし,労基署への届け出まで一貫して対応が可能です。
③ 賃金・労働時間・休日等の明示と説明責任
労働条件のうち,賃金・労働時間・休日・休暇は,特にトラブルの原因となりやすい項目です。外国人労働者の場合,「固定残業制」や「みなし労働時間制」の仕組みに不慣れであるため,誤解を避ける説明が必要です。
- 法定労働時間と所定労働時間の違いを丁寧に説明する
- 時間外労働・深夜割増の計算方法を具体例とともに提示する
- 有給休暇の取得条件と,無断欠勤との違いを明確化しておく
- 通貨・支払方法・支払日など,賃金支払いの基本事項も口頭で確認する
一般的に社労士は,企業の業種・規模に応じた就業規則の作成や,労働契約書の内容チェックを行い,外国人労働者との誤解やトラブルを未然に防ぐ支援を行います。
また,弊社では多言語による説明資料の作成や,労働条件に関する社内説明会の実施もサポート可能ですので,お困りの場合はまずご連絡ください。
2-2.労務管理
外国人労働者を受け入れる企業にとって,労務管理は最も注意すべきポイントの一つです。単なる勤怠管理や給与計算にとどまらず,「在留資格」「言語・文化」「生活習慣」「労働観」など,複数の要素が交錯しています。労使トラブルや誤解を防ぎつつ,法令に沿った適正な運用が求められます。
① 勤怠管理・残業管理
- 外国人労働者に対しては,労働時間の考え方(休憩・残業・深夜・休日労働)について明確に説明し,就業前オリエンテーションでの理解をしてもらうことが大切です。
- タイムカード・システム運用の適正化や,みなし残業制導入時の労使協定整備を支援し,不当な長時間労働や未払い残業を防ぎましょう。
② 給与計算
- 社会保険料,所得税,住民税などの法定控除項目の説明は,特に外国人にとって不明瞭になりやすく,トラブルの温床となるため,やさしい日本語を交えてしっかり説明しましょう。
- 給与関連の制度説明・個別相談にも対応し,外国人労働者にとって安心して働ける環境を作りましょう。
- 外国送金(母国への仕送り)との両立を考慮した給与設計も必要な場合があります。送金時の税務影響や就労ビザの要件も踏まえて対応することが望ましいです。
(例:年額38万円以上を母国にいる家族に送金する場合,源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならない 等)
③ 社会保険・労働保険の運用
- 外国人であっても,日本人と同様に各種保険の適用義務があります。例えば「週20時間以上」の労働であれば,原則雇用保険への加入が必要です。
- 「技能実習生」や「短時間パート」のようにケースバイケースで判断が分かれる点も多いため,適用基準の整理・制度説明・手続き代行を一括でサポートできる専門家に相談すると良いでしょう。
④ メンタルヘルス・多文化職場への対応
- 外国人労働者にとっては,慣れない日本での生活や就労環境が,孤立・不安を感じやすいというリスクがあります。
- 外国人向け相談体制(第三者窓口の設置,ハラスメント相談の体制づくり)の設計や,多文化共生研修の実施支援などを通じて,メンタルヘルス対策を支援しましょう。
- 特に中小企業では,社内に専門人材が不在な場合も多いため,社労士が「外部の人事部門」として,継続的に関わることがも可能です。
2-3.社会保険・労働保険の手続き
外国人労働者を雇用する際も,日本人と同様に社会保険(健康保険・厚生年金)および労働保険(雇用保険・労災保険)への加入義務が発生します。
社労士は,次のような業務を通じて,実務負担の軽減と制度運用の適正化に対応することができます。
被保険者資格の取得・喪失手続きの代行
- 雇入れ時の資格取得届,退職時の資格喪失届,離職証明書作成など,煩雑で期日厳守が求められる手続きを代行します。
- 技能実習生や短時間パートなど,適用除外の可能性があるケースの判断も社労士が整理・助言します。
保険料の計算と納付管理
- 報酬月額・標準報酬月額に基づく社会保険料の算定や,雇用保険料率の年度更新対応などを含む,定期的な事務作業もサポートすることができます。
- 保険料控除の根拠を説明し,外国人労働者本人への明細説明資料の作成なども支援可能です。
各種給付金の申請支援
- 出産手当金,傷病手当金,失業給付,労災給付など,給付制度の案内と申請支援を実施します。
- 外国人労働者が制度を知らずに申請の機会を逸するケースを防止するため,やさしい日本語・外国語での制度案内文書の作成も可能です。
制度の理解促進と相談対応
- 外国人労働者にとっては,「保険制度の意義」「自国との制度の違い」「将来受けられる年金・医療の内容」などが分かりにくい場合が多く,制度の説明を行うことも効果的です。
- 社労士は,企業の制度説明体制の構築支援や,外国人労働者向けの質問対応代行(社外ヘルプデスク的な役割)も担うことができます。
その他にも,外国人といえば「在留資格(いわゆる「ビザ」)」の手続きも必須となりますが,在留資格(ビザ)の申請に関する手続きは「行政書士」または「弁護士」の業務となります。
第一綜合グループでは,行政書士と社労士が連携してワンストップで対応を行うことが可能です。どのようなお悩みでも構いませんので,まず一度,お気軽にご相談ください。
いつものお問い合わせ先
3.外国人雇用に関する法律と注意点
外国人雇用において,複数の法律を正しく理解し,遵守することが極めて大切です。この章では,外国人雇用を行う上で特に留意すべき法令とその実務上のポイントについて,社労士の視点からわかりやすく解説します。
3-1.労働基準法
労働基準法は,労働時間,休憩・休日,賃金,解雇など,労働条件に関する最低基準を定めた法律であり,日本人・外国人問わず,すべての労働者の人権と生活の安定を守る目的で運用されています。
主なポイント
- 法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える労働には,時間外労働協定(36協定)の締結と届出が必要である
- 時間外・休日・深夜労働には,法定の割増賃金を支払う義務がある
- 地域別最低賃金や,特定最低賃金の遵守(都道府県ごとに異なる)する
- 違法な解雇や不当な労働条件の強制は,重大な労基法違反となる
外国人労働者の中には,こうしたルールを知らないまま従事しているケースもあるため,企業は就業前にルールを丁寧に説明し,理解を促す体制が必要です。説明資料をやさしい日本語や母国で整備することも有効です。
なお,労働条件に関するトラブルが発生した場合には,労働基準監督署が相談窓口となります。社労士は,こうした状況の未然防止に向けた契約書や就業規則の整備支援,労基署対応のアドバイスを対応することができます。
3-2.出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)は,外国人の入国・在留・退去に関するルールを定めた法律です。外国人を雇用する企業にとっては,「その外国人が,就労可能な在留資格を保有しているか」を確認することが最も重要です。
主なポイント
- 在留カードの確認と記録(雇入れ・退職時)について
- 在留資格の種類(技術・人文知識・国際業務,特定技能など)について
※入管法では,外国人労働者が行う業務と,在留資格の種類が一致していることが求められます。 - 在留期間の管理(変更・更新手続き等)について
- 週28時間制限のある資格外活動者(例:留学生・家族滞在)の勤務時間管理について
特に,就労不可の資格保持者を雇用してしまった場合,企業側も「不法就労助長罪」で罰則の対象となります。担当者が「知らなかった」では済まされないため,細心の注意を払いましょう。
※「外国人雇用状況の届出(雇入・離職時)」の義務も企業に課されており,これを怠ると30万円以下の罰金対象となる可能性があります。
3-3.その他関連法規
外国人雇用は,上記で紹介した労基法や入管法だけでなく,複数の関連法規との複合的な運用が必要です。以下にて,代表的な法律と,それぞれに求められる対応をご紹介します。
労働安全衛生法
外国人労働者にも,安全で衛生的な労働環境の提供が求められます。
言語の壁がある場合は,翻訳された安全衛生マニュアルの整備や,災害時の避難訓練の多言語対応などが効果的です。
雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法
適用条件を満たす場合,外国人労働者も日本人同様に社会保険に加入させなければなりません。
※制度ごとに条件が異なりますが,代表的なものは以下のとおりです。
① 雇用保険(失業保険など)
原則:週20時間以上働く + 31日以上雇用見込みがある人
※アルバイトやパートでも上記を満たせば加入対象になります。留学生など「資格外活動」で働く人も,条件を満たせば原則加入が必要です。
② 健康保険・厚生年金保険(社会保険)
原則:正社員または週30時間以上働く人
※週20時間以上でも,一定条件を満たすと加入対象になる場合もあります。外国人も加入義務があります。
これらを正しく把握し,外国人労働者に長期的に働いてもらえるようにすることが大切です。トラブルを防ぎながら企業の信頼性向上にも繋げましょう。
4.自社に合った社労士を選ぶには?
外国人雇用を成功させるためには,信頼できる社労士の存在が欠かせません。ここでは,自社に合った社労士を選ぶためにチェックしたいポイントをご紹介します。
4-1.ポイント①:専門分野を確認しよう
社労士を選ぶ際には,検討している社労士の専門分野を確認しましょう。
社労士は基本的に労務管理,労働法などに精通していますが,外国人雇用に関するご相談をしたい方は,その社労士が入管法,労働基準法,労働契約法など,幅広い法律知識と実務経験を有しているかをご確認ください。
また,特定の業種に特化した社労士も存在します。製造業・飲食業・ITなど業種特化型の社労士もいるので,自社の業界に強い人を選ぶとより専門的なアドバイスを受けることができるため安心です。
4-2.ポイント②:実績があるかチェック
依頼を検討する際は,事前にウェブサイトやパンフレットにある支援事例・お客様の声・セミナー実績などを見て,信頼できるかを判断しましょう。
例えば,外国人雇用のサポート経験が豊富な社労士は,さまざまなケースに対応したノウハウを持っています。
また,セミナーや講演会などの活動を通じて,情報発信を行っている社労士もいます。実績豊富な社労士は,手続きの正確性やスピード,トラブル対応能力など,様々な面で信頼につながります。
4-3.ポイント③:費用体系を事前に確認
社労士の費用は依頼内容や業種・業態によって異なります。社労士の業界でよくある形態は以下のとおりです。
顧問契約
毎月定額で継続的なサポートを受けられる契約形態です。
会社の状況を把握したうえで,社内の実情に沿った相談や助言をタイムリーに行えることが特徴です。
スポット契約
要な手続きや案件だけを単発で依頼できる契約形態です。
すでに顧問社労士がいるものの,その社労士の専門外の業務だけを依頼したい場合や,社内で基本的な労務管理は対応できるが,専門性の高い部分のみ外部に任せたい場合に利用できることが特徴です。
4-4.ポイント④:対応の丁寧さ・スピード
社労士を選ぶ際には,対応の質も重要なポイントです。
相談に対するレスポンスの速さ,丁寧な説明,親身な対応など,コミュニケーション能力も重要な要素です。初回の問い合わせに対する対応や,面談時の説明の分かりやすさ等,社労士との相性を確認しましょう。自社の立場に立って考えてくれる,話しやすく信頼できる社労士であるかも大切な判断材料です。
信頼できる社労士をパートナーにすることで,安心して外国人雇用に取り組める体制が整います。
5.成功事例と失敗事例から学ぶ,外国人雇用
外国人雇用は,単なる人材確保の手段ではありません。制度の理解不足や受け入れ体制の不備により,トラブルや定着率の低さにつながるケースも少なくありません。
過去の事例を分析し,「うまくいった企業の共通点」「失敗した企業が見落としたポイント」を明らかにし,自社の体制にも活かせるよう,成功事例と失敗事例を比較しながら,外国人雇用を成功に導くための具体的なヒントを探っていきましょう。
5-1.成功事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業概要 | 国内外で事業を展開するIT企業。人手不足解消と技術力強化のため外国人を採用 |
| 雇用した人材 | 外国人エンジニア(技術・人文知識・国際業務ビザ) |
| 成功の ポイント | ・明確な採用基準の設定 必要なスキル・経験・日本語レベルを数値化し,ミスマッチを防止した。 ・丁寧な選考プロセス 複数回の面接を通じて,スキル・価値観・文化適応性を総合的に評価した。 ・受け入れ体制の整備 入社時オリエンテーション,日本語研修,業務マニュアルの多言語化を進めた。 ・多文化共生の社内風土 社内イベントや,外国籍社員向けのメンター制度を導入し,孤立しないように社内全体で努めた。 |
この会社での取り組みは,「採用時の基準明確化」と「受け入れ後のフォロー体制」の両輪が整っていたことが成功の決め手でした。また,社労士との連携により,法令をしっかりと守りながら労働環境を安定につなげることができました。
5-2.失敗事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業概要 | 首都圏で複数店舗を展開する飲食チェーン。外国人アルバイトの採用を進めていた。 |
| 雇用した人材 | 留学生(資格外活動許可)・家族滞在者アルバイトなど |
| 成功の ポイント | ・コミュニケーション不足 日本語での指示が正しく伝わらず,業務ミスが頻発し,既存労働者・外国人労働者の双方に不信感が募った。翻訳や通訳の工夫もされていなかった。 ・労働条件の不明確さ 就業前に労働条件通知書を交付しておらず,時給,残業代の支払いやシフト変更を巡ってトラブルが発生。 ・サポート体制の不備 日本語教育や生活サポートが皆無で,相談できる相手も不在。新生活への適応ができず,短期離職が相次いだ。 ・コンプライアンスの欠如 週28時間を超えてシフトを組んでしまい,入管法違反となる恐れがあった。また,労働法や在留資格に関する社内知識が不足していた。 ・社労士等の専門家との連携不足 労働条件の整備や在留資格管理を自己流で進めた結果,制度違反や法的リスクが顕在化した。 |
上記の失敗からは,制度理解不足と準備不足が複合的にトラブルを招くことが見て取れます。
特に「雇用契約書・労働条件通知書の不交付」「28時間超過勤務」「指導体制の不備」は,外国人雇用における典型的な失敗パターンです。不明点があったときも,社労士等の専門家を活用せず独自対応に頼った点も,法令違反リスクを高めた要因といえます。
5-3.成功事例と失敗事例から学ぶ,成功のポイント
過去事例の比較から,以下に成功のポイントをまとめましたので,ご説明します。
明確な採用計画の策定
自社にとって「どのようなスキル・在留資格・言語レベル」の人材が必要かを,事前に明文化しておきましょう。これにより,採用後のミスマッチを防止できます。
適切な採用方法の選択
ハローワーク,求人サイト,人材紹介会社,学校連携など,自社に合ったチャネルを見極めて活用しましょう。近年は多言語対応の求人サイトも増えているため,アプローチしたい国籍や年齢層に応じて選定することが大切です。
十分な事前準備
労働条件通知書や就業規則の整備,在留資格との整合性の確認など,専門家と相談しながら必要な制度準備を入社前に完了させましょう。
丁寧なコミュニケーション
日本語の壁を考慮し,やさしい日本語や翻訳ツールを活用しましょう。文化の違いを理解したうえで,双方向の対話を心がけることが重要です。
充実したサポート体制の準備
日本語研修,生活支援,相談窓口の設置,メンター制度など,就業以外の面でも安心できる体制を整えましょう。
コンプライアンスの徹底
労働基準法,入管法,資格外活動制限などの関係法令を正しく理解し,順守を徹底しましょう。法令違反を未然に防ぐ体制整備が求められます。
6.まとめ
人手不足が深刻化する中,外国人雇用は多くの企業にとって避けて通れない課題となりつつあります。外国人雇用には,労働力確保や多様性の創出といった大きなメリットがある一方で,在留資格や労働条件,労務管理などでつまずきやすいポイントも存在します。
しかし,本コラムで取り上げた内容をもとに,採用前から受け入れ後まで,計画的に体制を整え,専門家のサポートも活用しながら,外国人労働者との良好な関係と組織の成長の両立を目指しましょう。
今後,外国人雇用を検討・強化したいとお考えの企業様は,まずは信頼できる社労士に相談するところから始めてみてください。
この記事の監修者
社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛
- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)
東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。