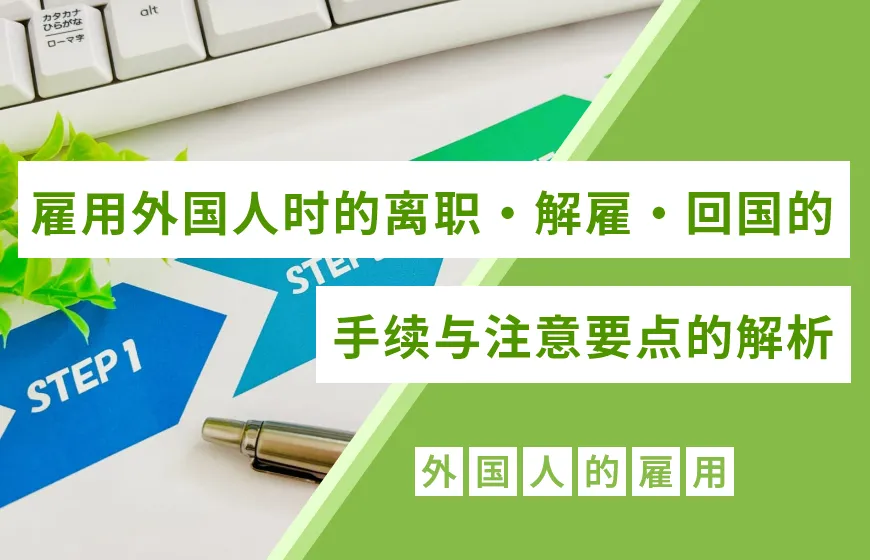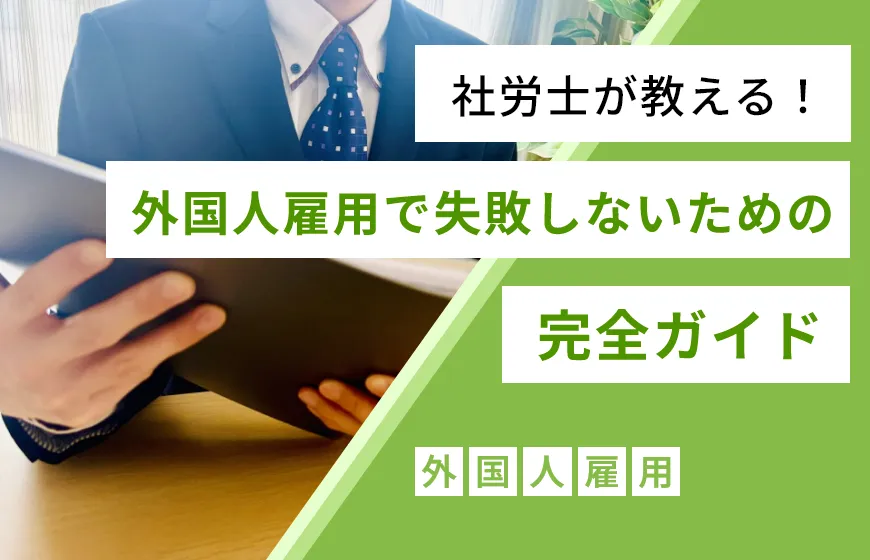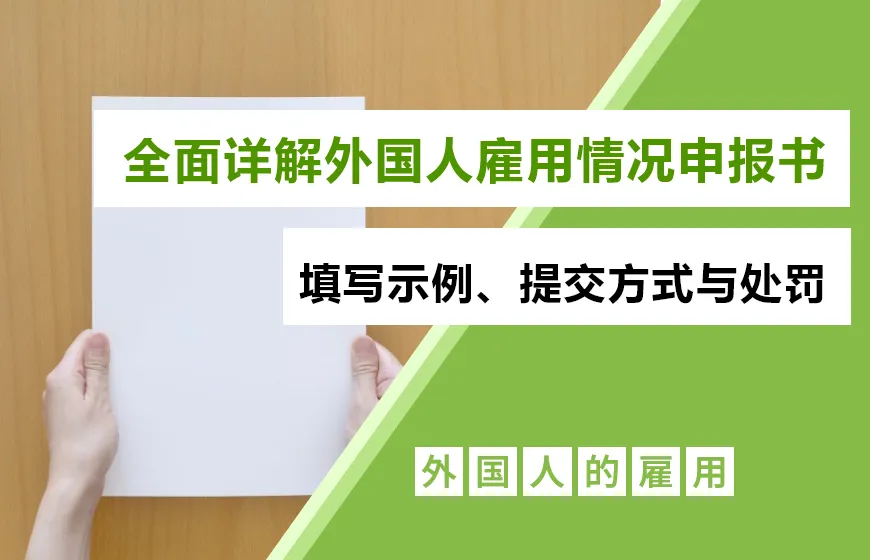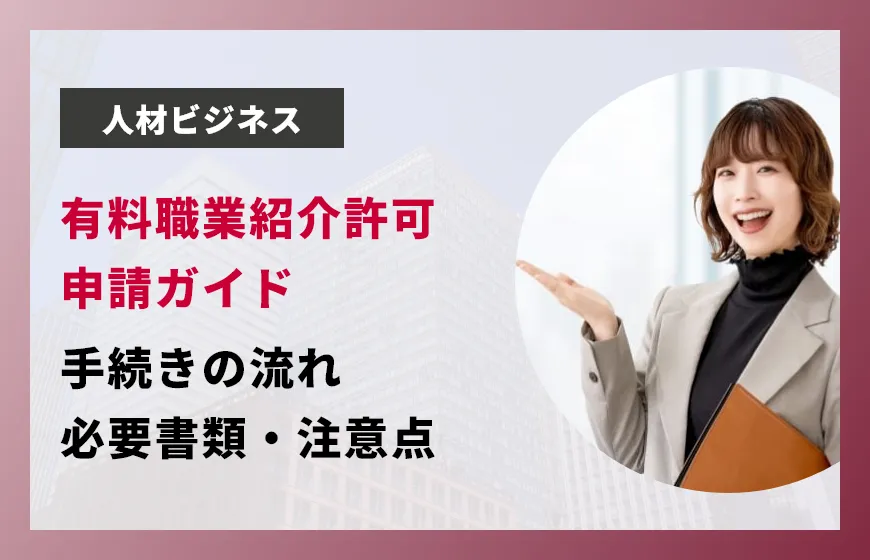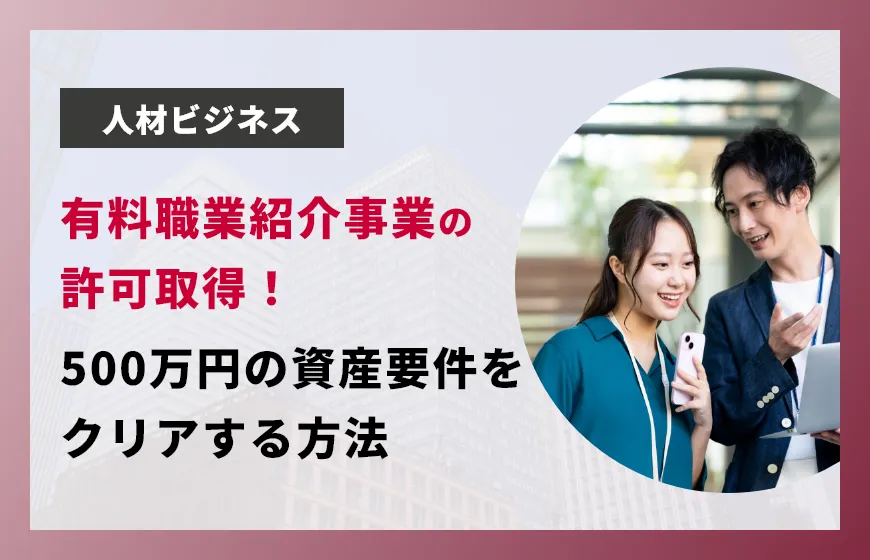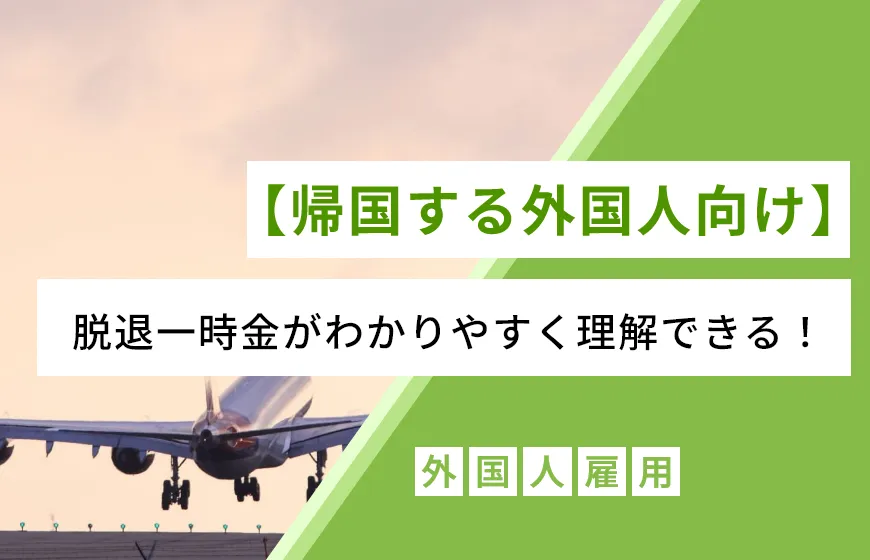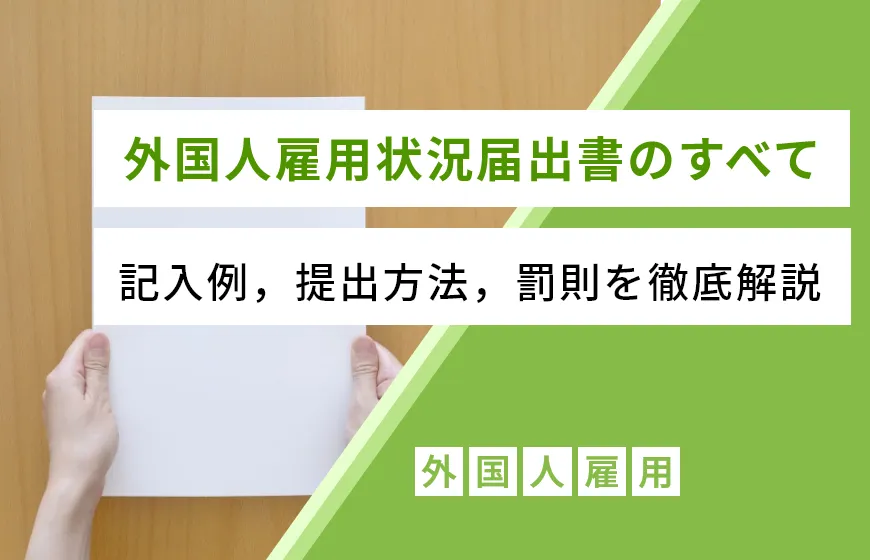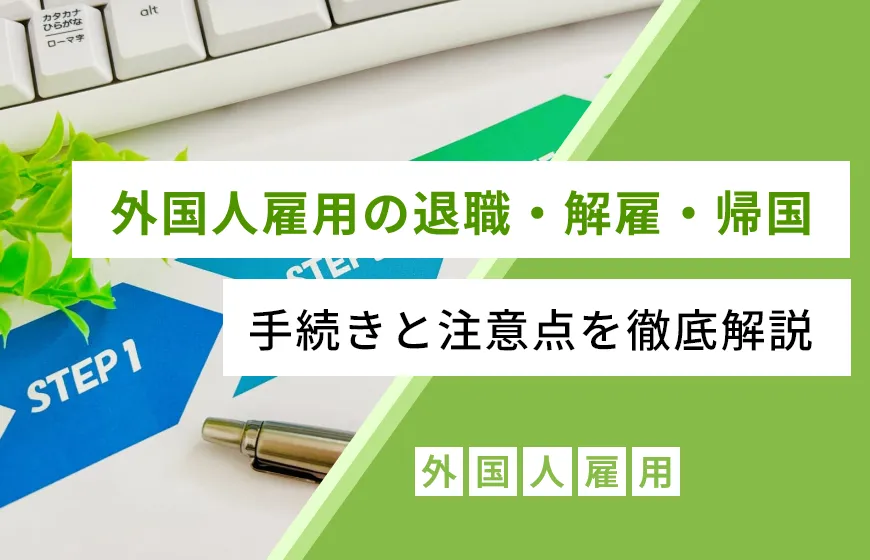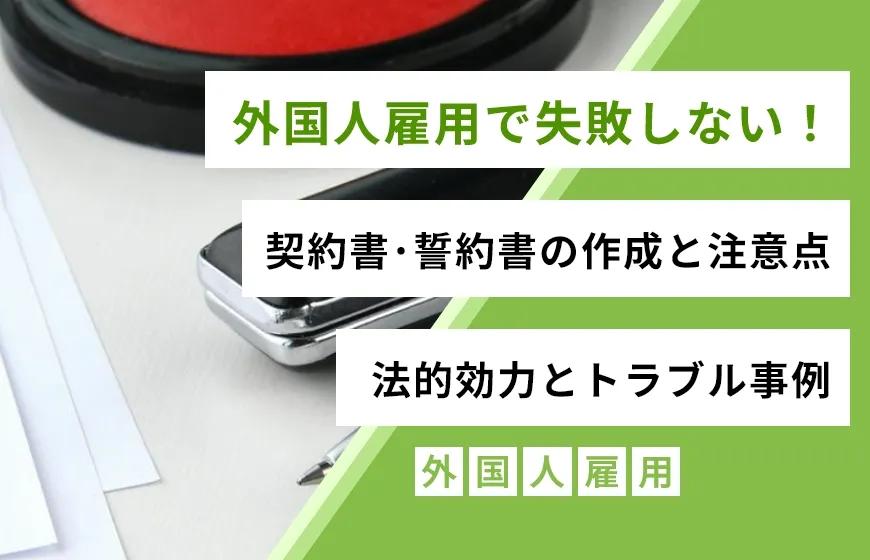
昨今,外国人雇用の流れが進む中,外国人雇用における「契約書」や「誓約書」の整備がますます重要視されています。「とりあえず日本人と同じ書式でいいだろう」と安易に対応してしまうと,トラブルが起きたときに企業側が不利になることも予想されます。
本コラムでは,外国人との雇用契約に必要な基本知識から,誓約書の法的効力,多言語対応のポイント,実際にあったトラブル事例まで,社労士の視点で解説します。
まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!
目次
1.外国人雇用における契約書と誓約書の重要性
外国人労働者を雇用する際には,「雇用契約書」と「誓約書」の整備が必要です。
これらの書類は,雇用者と労働者双方の権利・義務を明確にし,トラブルを未然に防ぐための重要な手段となります。特に,言語や文化の違いがある外国人労働者に対しては,より明確で丁寧な取り決めが求められます。
1-1.契約書と誓約書で防げるトラブルとは?
適切な雇用契約書や誓約書を取り交わすことで,以下のようなトラブルを未然に防止できます。
賃金未払いの防止
労働時間,残業代,給与支払いの条件などを明記することで,労働者との認識ずれによる誤解やトラブルを回避できます。
不当解雇の防止
解雇になる理由や予告期間などを明文化することで,実際に解雇することになった場合に紛争化する法的リスクを軽減します。
労働条件の認識相違の防止
勤務時間,休日,福利厚生などの条件を明確にすることで,労働者との認識のずれを防ぎ,信頼関係の構築につながります。
情報漏洩リスクの軽減
秘密保持義務や競業避止義務に関する誓約を設けることで,機密情報や顧客情報の漏洩を防止できます。
服務規律違反の防止
就業規則や服務規律の内容を事前に明示することで,労働者による違反行為の抑止につながります。
割増賃金の未払いや有給休暇の未付与など,労働基準法をはじめとする労働関係法令に違反した場合は行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
企業としては,こうしたリスクを回避するためにも,契約書・誓約書の作成・管理を法令に則って適切に行う必要があります。
また,誓約書についても,記載内容によっては法的効力を持つ場合があります。たとえば,秘密保持に関する誓約書は,情報漏洩が発生した際に損害賠償請求の根拠として利用できることがあります。
企業は,こうした点も踏まえたうえで,雇用契約書や誓約書を整備し,法令遵守の徹底を図ることが求められています。
2.雇用契約書の基礎知識
外国人労働者を雇用する際,適切な雇用契約書を交わすことで後々のトラブルを防ぎ,外国人労働者にとっても安心して働ける環境を整えることができます。
雇用契約書に記載すべき基本項目,労働条件通知書との違い,そして契約期間や試用期間における注意点について解説します。
2-1.雇用契約書に記載すべき項目
雇用契約そのものは,口頭によっても成立しますが,トラブル防止の観点からは,書面による雇用契約書を作成することが一般的です。特に外国人労働者との間では,言語や文化の違いによる認識のずれを防ぐため,書面での確認が不可欠です。
雇用契約書には,以下の内容を記載しておくとよいでしょう。
労働条件
始業・終業時刻,1日の労働時間,休憩時間,休日や休暇制度,有給休暇の付与時期・日数など,働く時間と休みに関する条件を具体的に明記しましょう。
賃金
基本給だけでなく,残業代,通勤手当,各種手当の有無,支払方法,締切日・支払日などを明確に記載します。特に残業の有無や,残業が発生した場合の割増賃金の支払いについても明記しておきましょう。
※固定残業制度を導入している場合は,固定残業手当に相当する金額及び含まれる残業時間数を明記し,それを超える残業が生じた場合には別途残業代を支給する旨,就業規則に定めるなどの対応が必要です。
契約期間
有期雇用の場合は,契約の開始日・満了日を明示し,更新の有無や条件も記載します。無期雇用であれば「期間の定めなし」と記載しましょう。
就業場所
勤務する拠点や配属先を明記します。異動の可能性がある場合は,異動条件や範囲もあわせて記載すると安心です。
業務内容
職種名だけでなく,実際に従事する具体的な業務を記載しましょう。抽象的な表現は,入管へのビザ申請時に業務内容の誤解やトラブルの原因になります。また,業務変更の可能性がある場合はその業務範囲も記載しましょう。
解雇事由
どのような行為が解雇の対象となるのか,解雇の手続きや予告期間についても記載し,労働者の理解を得ておくと安心です。
社会保険の加入状況
正社員であれば,原則として雇用保険,健康保険,厚生年金への加入義務があります。パートやアルバイトでも条件を満たせば加入が必要となるため,どの保険が適用になるのか明示しましょう。
ビザ手続きに関する条件
就労できるビザを持っていることが前提となるため,ビザが取得できなかった場合は雇用を継続することができない旨も記載しておくことをおすすめします。
2-2.労働条件通知書との違い
雇用契約書と混同されがちな書類に「労働条件通知書」がありますが,両者には明確な違いがあります。
| 項目 | 雇用契約書 | 労働条件通知書 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 労使合意を証明する契約書 | 使用者が労働条件を通知する文書 |
| 法的義務 | 義務ではない | 作成・交付が法律で義務付けられている(労基法第15条) |
| 効力の根拠 | 双方の署名または押印により成立 | 通知書単体では契約成立を証明できない |
| ビザ申請 | 署名・押印があれば,雇用契約の疎明資料として使用可能 | 単体では使用が難しい契約の証拠としては不十分と判断される場合がある |
労働条件通知書には,すべての労働者に対して以下の項目を記載することが義務付けられています。
これらは「絶対的明示事項」と呼ばれ,雇用契約の締結時に書面または電子メール等で明示しなければなりません。
絶対的明示事項
- 労働契約の期間(有期契約か無期契約かの区別)
- 就業の場所(勤務地)
- 就業の場所の「変更の範囲」
- 業務の内容(職種)
- 業務の内容の「変更の範囲」
- 始業・終業時刻,所定外労働の有無
- 休憩時間,休日・休暇
- 賃金の額,計算方法,支払方法,締切日・支払日
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
~ 2024年4月からの法改正ポイント(有期契約への追加明示) ~
2024年4月の改正により,有期労働契約を締結・更新する際には,以下の事項を書面等で明示することが義務化されました。
明示が必要な項目
- 契約更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限,その有無・理由)
- 無期転換申込機会の有無
- 無期転換後の労働条件
※契約締結時・更新時のいずれのタイミングでも適用されます。
※詳しくは,厚生労働省ホームページをご覧ください。
また,近年では,これらを一体化した「労働条件通知書兼雇用契約書」という形をとる企業も増えています。法的義務の履行と,契約合意の証明を一括で対応することが可能になります。
2-3.契約期間,試用期間の注意点
契約期間
有期雇用契約の場合は,契約満了時に更新の有無・更新条件を明記しましょう。この点が曖昧なままだと,更新の期待権が発生し,契約満了時にトラブルに発展する可能性があります。
無期雇用の場合は,その旨を明示しましょう。
試用期間
試用期間は1か月から6か月程度が一般的ですが,法律上の上限はありません。ただし,あまりに長い試用期間は「合理性がない」と判断されるおそれがあり,無効とされるケースもあります。
また,試用期間中に解雇を行う場合には,就業規則や雇用契約書に「試用期間中の解雇」について明確な定めが必要です。
たとえば,「適性が認められない場合には本採用を行わないことがある」といった文言を記載しておくとよいでしょう。
3.誓約書の作成ポイント
外国人労働者を雇用する際,雇用契約書に加えて「誓約書」を取り交わしておくことで,トラブルの防止や企業のリスク管理に役立ちます。
ここでは,誓約書に盛り込むべき具体的な内容や,作成時における注意点,法的効力について解説します。
3-1.誓約書に含めるべき具体的な内容
誓約書は,企業と労働者の間で合意した「就業上のルール」や「守るべき義務」を明文化するための書面です。外国人労働者との間でも,日本人と同様に以下のような内容を記載することが一般的です。
秘密保持義務
勤務中に知り得た企業の機密情報(顧客情報・営業戦略・技術情報など)を,在職中はもちろん,退職後も第三者に漏らさないことを誓約させます。
また,「秘密情報」の範囲や内容を明確に定義し,違反時の損害賠償責任の有無についても明記しておくことが重要です。
服務規律の遵守
就業規則や服務規律(遅刻・欠勤の連絡方法,服装規定,ハラスメント防止など)を守ることを明記し,企業内の秩序維持を図ります。とくに文化的背景が異なる外国人には,具体的な例示も効果的です。
その他の禁止事項・企業独自のルール
例として以下のような内容が含まれます
- 会社の承諾なく兼業・副業を行わないこと
- 会社の資産(PC・制服・備品など)を私的に使用しないこと
- SNS等での情報発信に注意すること など
業種や業務内容によってリスクのある行動を予防する目的で,企業ごとのルールを明記しておきましょう。
3-2.誓約書の法的効力と注意点
誓約書の法的効力
誓約書は,契約書と同様に法的効力を持つ場合が多く,署名または記名押印があれば,本人の意思による合意とみなされます。そのため,誓約内容に違反した場合には,損害賠償請求や懲戒処分の根拠にもなり得ます。
ただし,以下のような内容は無効とされる可能性がありますので注意が必要です。
- 労働基準法などの労働法令に反する内容
- 労働者の権利を不当に制限する内容
- 公序良俗に反する内容
作成時の注意点
内容は明確かつ具体的に
「誠実に勤務すること」「会社の名誉を毀損しないこと」など,抽象的な文言だけでは実務上の拘束力が弱くなります。できる限り,行動や範囲を定義したうえで記載しましょう。
署名・押印を必ず取得
誓約書は「誓約した」という証拠を残す文書です。当事者の署名または記名押印がない場合,法的な争いになった際に証拠能力が弱まります。
多言語での理解促進
外国人労働者向けに誓約書を作成する際は,日本語が十分に理解できるかどうかを確認し,必要に応じて母国語併記や口頭での補足説明を行いましょう。内容を理解していない誓約書に署名させることは,トラブルの原因になります。
誓約書は「義務を課す」だけでなく,「トラブルを未然に防ぎ,信頼関係を築くため」にも重要な意味を持ちます。外国人労働者の文化的背景や理解度にも配慮しながら,実効性のある内容で作成することがポイントです。
4.多言語に対応した契約書の作成
外国人労働者を雇用するにあたっては,雇用契約書や誓約書を多言語で作成することが近年重要視されています。
言語の壁による認識のズレを防ぐことで,安心して働ける環境を整え,労使トラブルのリスクを大幅に軽減することができます。
4-1.契約書の多言語化の必要性
外国人労働者の中には,日本語を日常会話レベルで話せても,読み書きに不安があるケースが少なくありません。そのため,日本語のみで作成された契約書では,内容を正確に理解できず,後に誤解や不満を生む原因となるおそれがあります。
企業側が外国人労働者に母国語で契約内容を提供することは,「安心感」や「信頼関係」の構築にもつながります。
また,入国管理局への在留資格の申請時には,労働条件通知書の外国語訳の提出が求められる場合もあり,正確な翻訳が欠かせません。
このような背景から,契約書の多言語化は,単なる言語配慮ではなく,法的・実務的にも極めて重要な対応であるといえます。
4-2.翻訳の注意点
契約書を多言語に対応させる場合,以下のようなポイントに注意して翻訳作業を進めましょう。
法務・労務の知識がある翻訳者に依頼する
翻訳者には,法的表現や労務用語に対する理解が必要です。一般的な翻訳では意図が正確に伝わらないことがあるため,法律や人事労務に関する専門知識を持つ翻訳者への依頼が望ましいです。
原文の日本語を明確にする
誤訳の多くは,原文のあいまいさや誤記が原因となっています。翻訳前に必ず,日本語の契約書の文面が正確で論理的に整っているかをチェックしましょう。
ダブルチェック体制を整える
翻訳後は,第三者による確認(ネイティブチェックや専門家レビュー)を必ず実施してください。一見正しそうな翻訳でも,文化的背景や言語ニュアンスの違いにより,誤解を生む表現が含まれていることがあります。
テンプレートの活用も有効
厚生労働省や各自治体では,外国人労働者向けの労働条件通知書・契約書の多言語テンプレートを公開しています。英語・中国語・ベトナム語・ネパール語など多様な言語に対応しており,これらをベースに自社の内容を加筆することで,比較的スムーズに対応が可能です。
第一綜合グループでは,外国人の雇用管理やビザ申請など,国際業務に特化した支援体制を整えています。
就労資格の確認や在留手続きはもちろんのこと,外国人労働者に必要な雇用契約書・労働条件通知書の作成支援も多言語で対応可能です(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など。その他言語もご相談いただけます)。
さらに,労務管理については社会保険労務士が,在留資格関連は行政書士がそれぞれ担当することで,法令に基づいた外国人雇用の運用をワンストップでご支援しています。
実務対応に不安がある場合や,契約書まわりでお困りの際は,お気軽にご相談ください。
5.トラブル事例と対策
外国人労働者との雇用においては,言語や文化の違い,制度への理解不足などが原因で,思わぬトラブルが発生することがあります。中でも「賃金未払い」や「不当解雇」は,企業側にとって大きな法的リスクとなり得る重大な問題です。
ここでは,実際に起こり得る事例をもとに,その背景と具体的な防止策について解説します。
5-1.賃金未払い・不当解雇に関する事例
【事例1】残業代の未払い
ある企業が,固定残業代制度を導入して外国人労働者を雇用していました。
しかし,実際の残業時間が固定で定めた残業時間を大幅に超えていたにもかかわらず,追加の残業代を支払わなかったことが発覚。労働基準監督署の指導により,未払い分をさかのぼって支払うこととなりました。
企業側が取るべき対策
- 固定残業代制度の正しい理解と運用を徹底しましょう。
固定残業代はあくまで「一定時間分まで」を前提としており,超過分は別途支払い義務があります。 - 実労働時間の定期的なモニタリングを行い,実態と制度が乖離していないかを確認する体制を整えましょう。
- 管理職や現場責任者に対し,固定残業代制度の運用ルールと法定義務に関する研修を実施しましょう。
- 勤怠記録と賃金計算が自動連携するシステムの導入も,人的ミスや対応漏れを防ぐ手段として有効です。
【事例2】不当解雇
外国人労働者に対し,「能力不足」を理由に解雇を通告した企業がありました。
しかし,実際には十分な指導や教育を行っておらず,労働者に改善の機会も与えていなかったため,解雇の正当性が否定されました。結果として,企業側には解雇の撤回と,解雇期間中の賃金の支払いが命じられました。
不当解雇を防ぐための対策
- 解雇の前には,具体的な指導や教育の実施,配置転換の検討など,改善の機会を設ける必要があります。
- 解雇を検討する際は,「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ,無効とされる可能性があります。
- 就業規則や雇用契約書に明確な解雇事由を記載しておきましょう。
- 外国人労働者に対しても,就業規則などを母国語や英語で説明・共有することが望まれます。
6.まとめ
今回は,外国人労働者の雇用において欠かせない雇用契約書・誓約書などの書類作成とその注意点について解説しました。
これらの書類を正しく整備することは,労使双方の信頼関係を築く土台となるだけでなく,将来的なトラブルを未然に防ぐリスク対策としても役立ちます。
また,労働基準法や入管法などの法令を遵守した書類を作成するためには,社会保険労務士や行政書士への相談や書類作成サポートを活用することもご検討ください。
第一綜合グループでも,外国人雇用に関するご相談を多数承っており,在留資格の確認や契約書作成,就業規則の整備まで,実務に即したサポートを一貫してご提供しております。
この記事の監修者
社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛
- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)
東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。