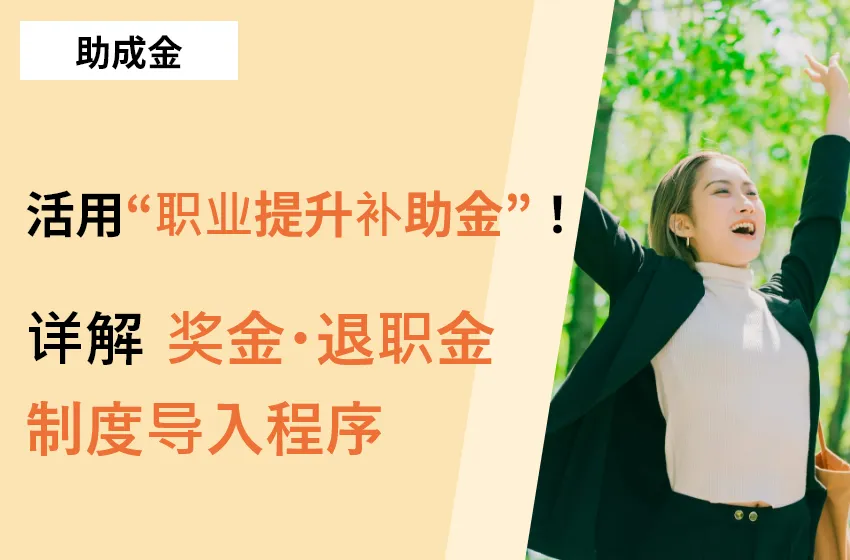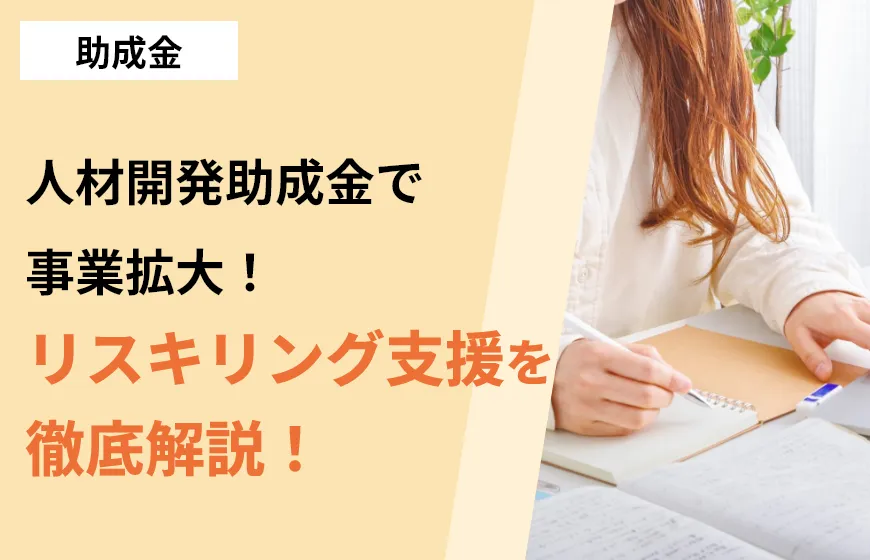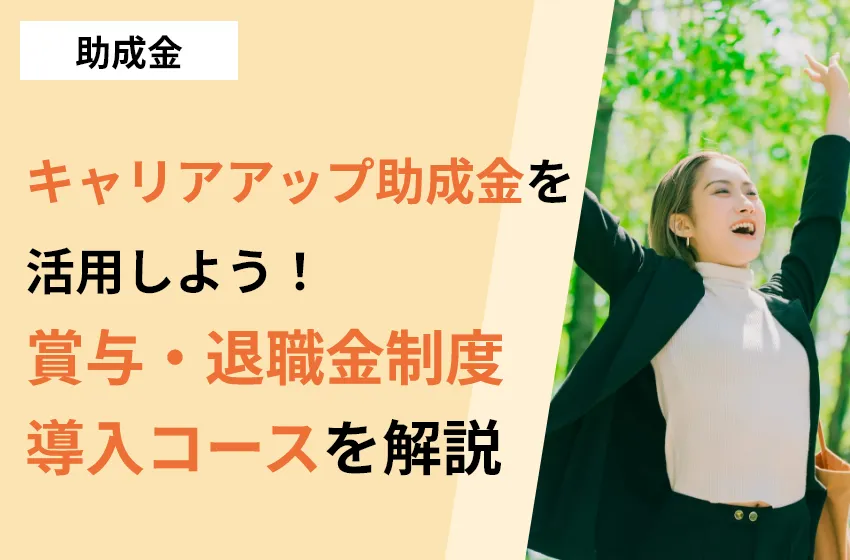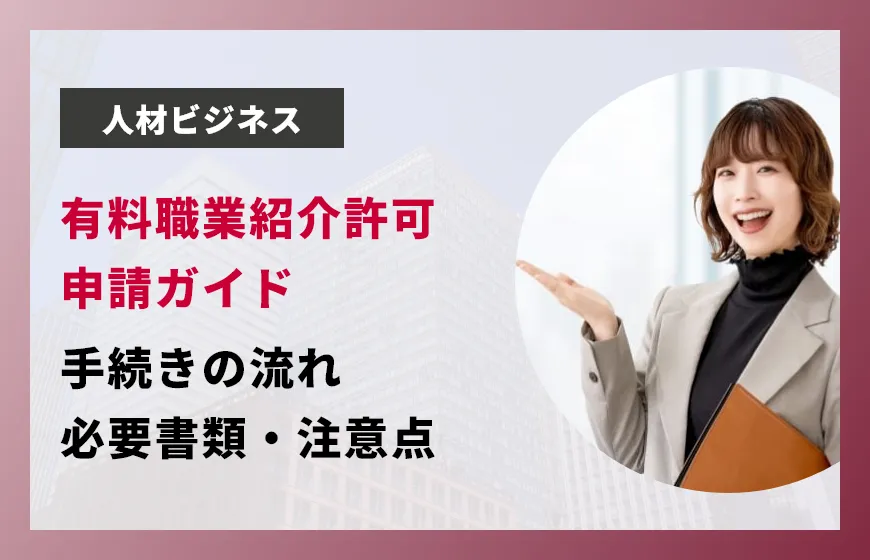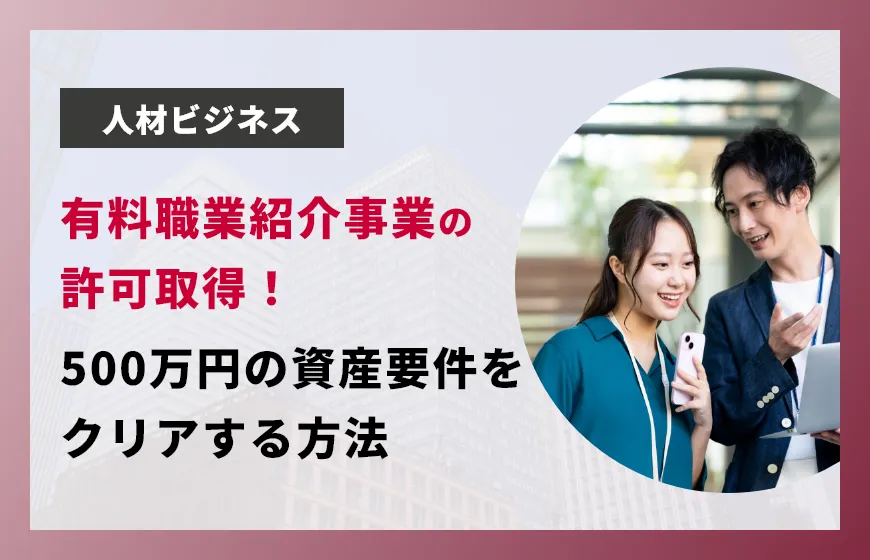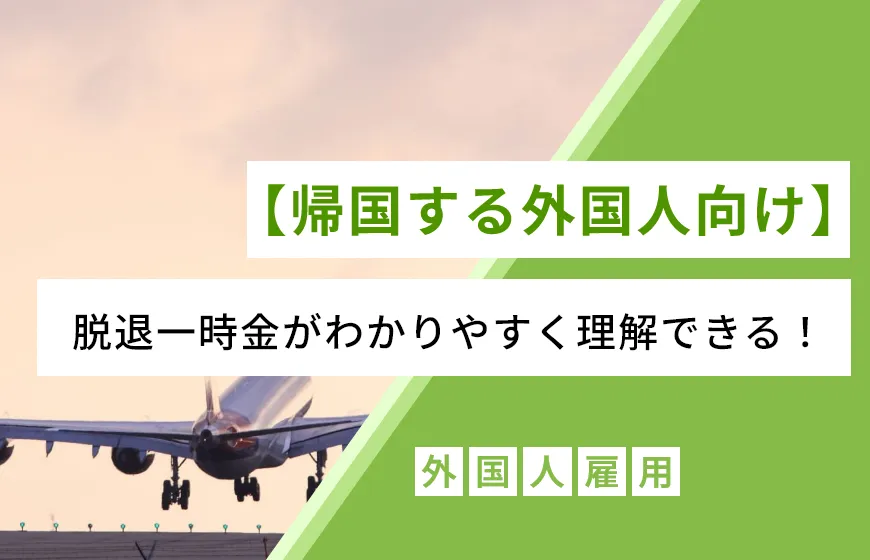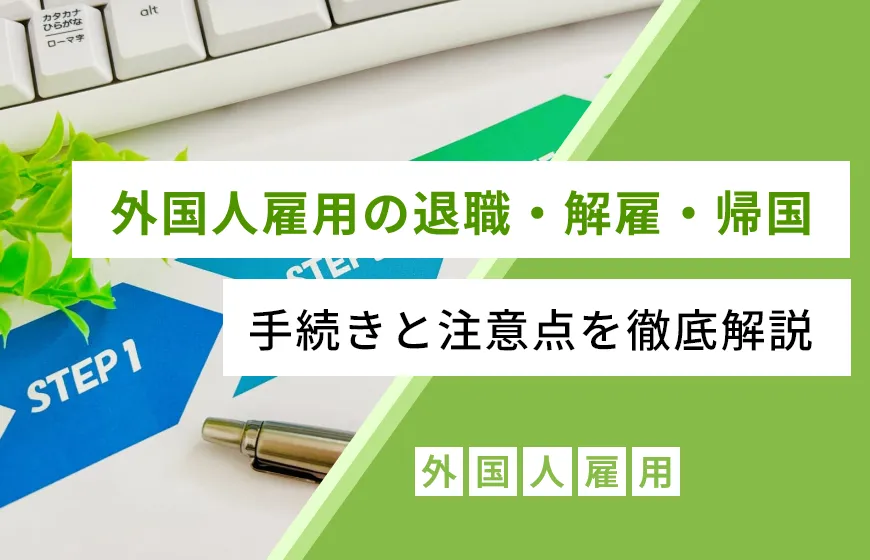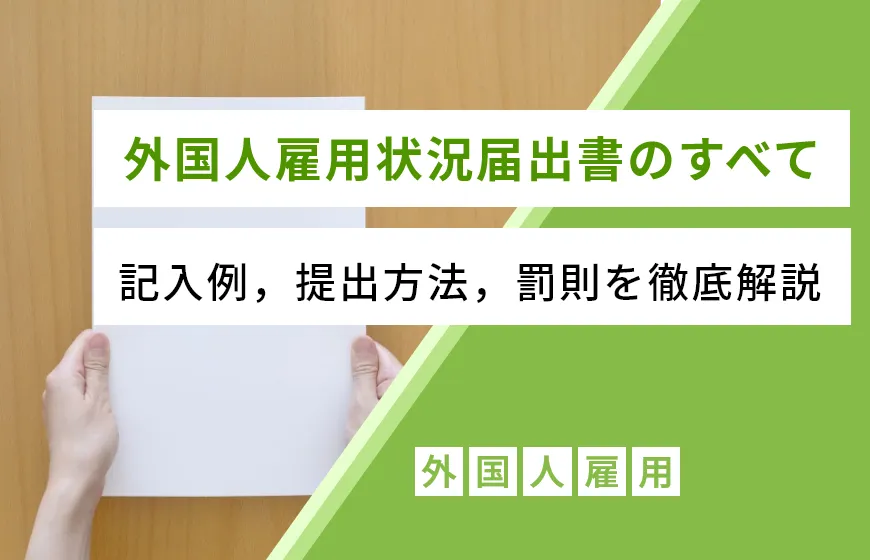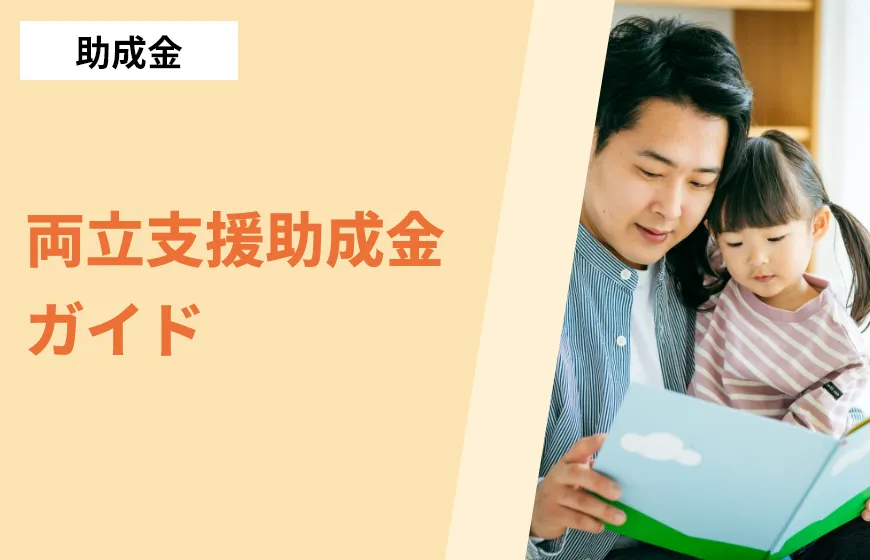
本コラムでは,両立支援等助成金についてのご紹介と,利用できる助成金制度や申請に必要な情報をお伝えします。用意された制度を活用して,仕事と育児・介護との両立を実現させる企業の仕組み作りをしていきましょう。
まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!
目次
1.両立支援等助成金の種類と概要
出産や育児・介護等と仕事を両立することは,多くの人にとって近年大きな課題となっています。今回ご紹介する助成金は,子育てや介護をしながら働く人が仕事を続けやすくなるように,職場環境を整えた企業に対して,国から支給されるお金(助成金)です。具体的にどのような助成金があるのか,一つずつ見ていきましょう。
1-1.出生時両立支援コース
出生時両立支援コースは,通称「子育てパパ支援助成金」と言われ,男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制整備を行い,以下のような場合に事業者へ支給されます。
- 男性労働者が「子の出生後8週間以内」に開始する,「連続5日以上の育児休業」を取得した場合
- 男性の育児休業取得率が一定数以上上昇した場合 等
1-2.育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは,働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため,育児休業の円滑な取得,職場復帰に向けた取り組みを支援しています。
具体的には,以下のような場合に,企業に対して助成金が支給されます。
- 「育休復帰支援プラン」を策定の上,「労働者が連続3カ月以上」の育児休業を取得した場合
- 労働者の育児休業中に職務や業務の情報提供等を実施し,労働者が原職に復帰した場合
これにより,女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすくなり,男女共に仕事と育児の両立を支援する環境が整えることが可能になります。
1-3.介護離職防止支援コース
介護離職防止支援コースは,仕事と介護の両立を支援するために用意された制度です。
以下のような,柔軟な就労形態の制度を制定し,労働者が介護と仕事を両立できるような取り組みを行った企業へ助成金を支給します。
- 「介護支援プラン」を策定の上,労働者が「連続5日以上の介護休業」を取得,職場に復帰した場合
- 介護両立支援制度を導入し,利用した場合
これにより,介護離職をすることなく労働者が安心して,介護を行いながら仕事を続けられるように支援することができます。
2.助成金の対象者となる要件
この章では両立支援等助成金の対象となる要件を紹介します。労働者と事業主の要件,それぞれ異なる要件が定められていますので,しっかり見ていきましょう。
2-1.労働者の要件
まず,労働者側の要件をチェックしていきます。助成金の対象となるためには,以下の条件が必要とされています。
- 雇用保険の被保険者であること
雇用保険の被保険者となるには,週20時間以上の勤務が必要となります。 - 育児・介護休業を取得すること
各コースにより,最低取得日数が定められています。
各コースの最低取得日数
- 出生時両立支援コース → 5日以上の育児休業
- 育児休業等支援コース → 連続3ヶ月以上の育児休業
- 介護離職防止コース → 5日以上の介護休業
2-2.事業主の要件
続いて,事業主側はどのような要件が求められるのでしょうか?こちらもしっかりとチェックしていきましょう。
- 雇用保険適用事業主であること
事業の内容にかかわらず,雇用している労働者のうち一人でも雇用保険の適用対象となる場合は,その事業主は「雇用保険適用事業主」となります。
ただし,雇用している「すべての労働者」が雇用保険の適用対象外である場合には,適用事業主とはなりません。 - 育休業制度を整備し,実施していること
育児休業に係る研修の実施,相談体制の整備,育児休業の取得に関する事例の収集及び提供などが挙げられます。 - 就業規則を作成していること
育児休業,または介護休業に関する規定を就業規則に明記している必要があります。法令に則った内容であるか,確認をしましょう。 - 事業所規模が「中小企業」であること
上記で紹介した助成金制度は,どれも中小事業主である場合に支給対象事業主となります。中小事業主は以下の範囲となります。
| 小売業(飲食業含む) | 資本金・出資額が5千万円以下,または常時使用する労働者数が50人以下 |
| サービス業 | 資本金・出資額が5千万円以下,または常時使用する労働者数が100人以下 |
| 卸売業 | 資本金・出資額が1億円以下,または常時使用する労働者数が100人以下 |
| その他 | 資本金・出資額が3億円以下,または常時使用する労働者数が300人以下 |
2-3.その他要件
上記のような,労働者・事業所の要件の他にも,以下のような要件が設けられています。こちらも忘れず確認していきましょう。
- 過去の不正受給がないこと
過去に不正受給があった場合,当該不支給決定より5年間は助成金の対象外となります。 - 労働保険料の滞納がないこと
支給申請日の前年度より前の保険年度の労働保険料を支払っていない場合,助成金の対象外となります。(支給申請後2ヶ月以内に納付を行うと申請が可能となります。) - 労働関係法令に違反していないこと
支給申請日の以前1年間に,違反を行い送検されている場合は助成金を支給できません。
以上,自社が助成金の支給要件を満たしているかの確認を行い申請に備えましょう。また,申請後も引き続き法令遵守を徹底しましょう。
3.助成金の申請方法と必要書類
続いてここからは,申請の手順と必要書類について解説していきます。助成金申請のための手順と必要書類をしっかりと確認しながら,申請の準備を進めていきましょう。
3-1.申請手順
助成金の申請は,以下の手順で進められます。
- 計画の策定と提出
自社の状況に合わせて,就業規則等の規定化及び周知,休業プラン作成のための面談を行った後,計画策定に移ります。
具体的には,企業は育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に基づき,一定の計画を策定することが求められています。そのため,「次世代法に基づく一般事業主行動計画」を策定し,管轄の労働局へ届出を行う必要があります。 - 制度の実施
規定した制度に基づいて,育児休業や介護休業を実施します。 - 支給申請
定められた期日から,約2ヶ月以内に必要書類を揃えて都道府県労働局に支給申請を行います。また,申請方法には,以下の2つがあります。
①窓口での申請
管轄の労働局の窓口にて,直接申請書類を提出します。
受付時間や提出方法は労働局ごとに異なるため,確認が必要です。
※事前の予約は不要です。
②郵送での申請
宛先・必要書類・送付方法については,各労働局の公式サイトや事前連絡にて確認しましょう。
控えを返送してもらうために,返信用封筒(切手貼付・宛名記載)を同封するのが一般的です。
③電子申請
厚生労働省の「電子申請システム」を利用すれば,時間外や休日でも申請が可能です。
書類の郵送や窓口訪問が不要なため,忙しい中でも手続きを行える点がメリットです。 - 審査と決定
審査が行われ,助成金の支給が決定されます。なお,申請から支給までは一般的に2~3ヶ月程度かかります。
上記手順を踏まえ,労働者のそれぞれの事情を考慮しつつ,申請の準備を進めましょう。各手順や申請について不安や困ったことがあれば,専門家に頼ることで解決するケースも多くあります。弊社でもご相談の対応が可能ですので,お気軽にご連絡ください。
3-2.必要書類
不備が無いよう必要書類の準備を行いましょう。下記にて,必要な書類を説明していきます。
※コースによって必要な書類が一部異なるため,申請前に必ず申請予定のコースの要件をご確認ください。
- 申請書
支給申請書
支給要件確認申立書 - 事業所に関する書類
次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届 - 制度の実施状況を証明する書類
労働者の休業申出書
労働協約または就業規則
育児・介護休業規程 - 対象労働者の状況を証明する書類
出勤簿またはタイムカード
賃金台帳
労働条件通知書
母子手帳(出生時両立支援コース・育児休業等支援コースの場合) - その他
介護を受ける家族の介護保険被保険者証(介護離職防止支援コースの場合)
支払い口座が確認できる通帳等の写し 等々
申請書については,厚生労働省のホームページからダウンロードできます。コースごとに申請書類が掲載されていますので,ご確認ください。
なお,申請に必要とされる書類は量が多く,煩雑になっています。書類作成が困難な場合には社労士などの専門家へ相談し,申請代行を依頼することも検討してみましょう。
3-3.申請先
申請書類の準備が整ったら,労働局に申請します。申請先と申請方法について見ていきましょう。
申請先
両立支援等助成金の申請は,事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対して行います。
提出方法
申請書類は,以下のパターンがございます。
- 窓口へ持参
- 郵送で提出
※郵送の場合は,念のため,記録が残る形で送付することをオススメいたします。 - 電子申請
※近年,電子申請で行われるケースも増えています。電子申請であれば閉庁している時間帯や休日であっても申請が可能となります。
以上,申請手順や必要な書類,申請先をしっかりと確認し助成金の申請を行いましょう。
詳細は厚生労働省のホームページにも載っていますので,最新の情報のご確認も忘れないようにしましょう。
4.助成金の支給要件と受給額
両立支援等助成金の支給額はコースにより異なります。また,コースによっては申請回数に上限がある場合もあるため注意が必要です。確認不足で申請をすることができなかった!ということがないように,しっかり確認していきましょう。
4-1.受給額
本コラムで説明してきた「出生時両立支援コース」,「育児休業等支援コース」,「介護離職防止支援コース」の受給額について,下図にまとめています。適宜ご確認ください。
出生時両立支援コース
男性の育児休業取得時
1人目:20万円(30万円)
※()は雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合
2人目・3人目:10万円
男性育休取得率の上昇等
最大60万円
※申請年度の前事業年度と,前々事業年度を比較して男性育休取得率が30%以上UP&育休取得率50%以上
※1事業主1回限り
育児休業等に関する情報公表加算
2万円
※1事業主1回限り
育児休業等支援コース
育休取得時
30万円
※1事業所あたり2回まで
職場復帰時
30万円
※育休取得時と同一の対象者のみ対象
※1事業所あたり2回まで
育児休業等に関する情報公表加算
2万円
※1事業主1回限り
介護離職防止支援コース
介護休業取得・復帰時
40万円(60万円)
※()は連続15日以上休業の場合
※1事業主5人まで
介護両立支援制度の実施時 制度1つ導入及び利用
20万円(30万円)
制度2つ導入及び利用25万円(40万円)
※()は合計60日以上制度を利用した場合
※1事業主5人まで
環境整備加算
10万円
※1事業主1回限り
※雇用環境整備措置とは,職場において育児休業や介護休業を取りやすくするための環境づくりに関する取り組みで,以下のような内容が該当します。
- 育児休業や介護休業制度に関する研修の実施(労働者・管理職向け)
- 社内に育児・介護の相談窓口を設置と周知
- 育児休業事例の収集,事例の提供
- 育児休業制度,育児休業取得促進に関する方針の周知
- 育児休業の取得がスムーズに行われるようにするための業務配分や人員配置の措置
これらの措置を4つ以上実施し,所定の様式で報告することで,最大10万円の加算が受けられます。
また,育児休業に関する情報公表とは,企業のホームページや求人媒体などを通じて,育児休業取得実績や制度内容を公開することを指し,こちらも加算対象となります。
基本的な助成金制度の利用だけでなく,こうした加算措置も積極的にご検討ください。
5.申請におけるよくある質問と注意点
両立支援等助成金に関して,よくある質問を以下にまとめています。同じ悩みをお持ちの方の参考になりましたら幸いです。
5-1.よくある質問
Q1:育児休業等に関する情報公表の加算を企業が受けるためには,どの様な情報を公表する必要がありますか?
A:加算を受けるには,以下の3つの情報を「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」に掲載する必要があります。
- 男性労働者の育児休業等の取得割合
- 女性労働者の育児休業の取得割合
- 男女別の育児休業の平均取得日数
例えば,「前年度,配偶者が出産した男性労働者数のうち育児休業をした男性労働者数の割合が30%」など,具体的な数値を公表することが求められます。このような情報を外部に公表することで,職場の子育て支援への取り組みをアピールでき,助成金の加算対象にもなります。
Q2:同一事業主の事業所に勤務する父母が,同一の子の育児を理由に育児休業を取得する場合,それぞれについて申請は可能ですか?
A:はい,それぞれ個別に申請が可能です。
例えば,A社の営業部に勤務する夫と,同じA社の人事部に勤務する妻が,同じ子どもを育てるために交代で育児休業を取得した場合,夫・妻それぞれについて助成金の申請ができます。
ただし,取得期間や復職のタイミングなどに関して,各制度の細かい要件を満たしている必要があるので,事前に自分たちが要件に当てはまっているか等,専門家や市町村の担当者に確認しておくことをおすすめします。
Q3: 助成金の申請を,社労士やコンサルタントに依頼することはできますか?
A:もちろん,可能です。
助成金の申請代行は社労士のみが行うことができる「独占業務」です。
よくある誤解として,行政書士や民間コンサルタントなどに依頼されるケースがありますが,これらの方が申請代行を行うことは受任者(依頼を受けた側)の法律違反となります。そのため,申請をご検討中の方は,必ず社会保険労務士にご相談ください。弊社でも対応可能ですので,お気軽にご相談ください。
Q4:助成金が不支給になるケースはありますか?どんなケースですか?
A:以下のようなケースでは,申請しても助成金が支給されないことがあります。
- 申請内容に虚偽や誤りがあった場合
(例:取得日数の水増しなど) - 支給要件を満たしていなかった場合
(例:対象労働者が要件に該当していない) - 申請期限を過ぎてしまった場合
- 過去5年以内に,不正受給があった場合
- 労働保険料の滞納や法令違反がある場合
以上,申請前には,要件や提出期限,必要書類などをきちんとチェックしておきましょう。特に初めて申請される企業様は,社労士などの専門家に相談するのがおすすめです。
5-2.申請の際の注意点
よくある質問の他に,申請の際に意識したい点をお伝えします。ご確認いただき,確実に申請を行えるよう事前の対策に役立てば幸いです。
申請者の「単位」
両立支援等助成金は「事業主単位」の支給であり,事業所単位ではないことに注意が必要です。複数の事業所を運営する事業主の方は,間違いのないよう予め注意しておきましょう。
制度整備の実行時期
助成金を申請するには,休業を開始する前に労働協約や就業規則に休業規定を定め,明記する必要があります。また「育児介護休業法の内容による」との委任規定では不十分となります。そのため,休業前に社内制度を整えておきましょう。
申請期限の厳守
申請期限を必ず守りましょう。提出期限を過ぎると,申請を受け付けてもらうことができません。申請の準備は余裕を持って行うことをおすすめしております。確実に期限内に申請を完了させるためには,社労士のような専門家に相談することも一つの方法です。自社に合った方法を検討し確実に申請を行いましょう。
制度や支援プランの遵守
育児休業の期間や短時間勤務の条件など,申請に関する制度を遵守し介護休業の場合は休業プランに基づいた労働者への支援を行いましょう。遵守していない場合には助成金の返金を求められ,今後の申請が制限される可能性もあります。制度や支援プランの内容をよく理解し,計画的に進めていくことが重要です。
情報収集の際の注意点
育児介護休業に関する法改正は頻繁に行われ,それに伴い助成金の内容も改正されることがあります。申請前に最新の情報を市町村や厚生労働省のホームページなど調べ,要件を再確認しておきましょう。
以上,これらの点を参考に準備を進めていきましょう。その他の不明点がある場合は都道府県助成金センターに問い合わせることも重要です。社労士などの専門家に頼ることも方法の一つですのでご検討ください。
6.まとめ
本コラムでは,出産後の仕事と育児や,介護等を支援する「両立支援等助成金」について解説しました。いかがでしたでしょうか?
助成金の受給には,様々な条件をクリアする必要がありますが,制度作りを通じて,結果として労働者の定着率がアップし,人材募集の際においても企業をアピールできるポイントとなります。
今回ご紹介したような両立支援等助成金を活用し,労働者が安心して仕事と育児や介護に取り組めるよう支援をおこなっていきましょう。
社会保険労務士法人第一綜合事務所でもご相談を受けており,ご相談をいただいた際には弊社スタッフ一丸となって対応をさせていただきます。本コラムが,貴社における両立支援の一助となれば幸いです。
この記事の監修者
社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛
- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)
東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。